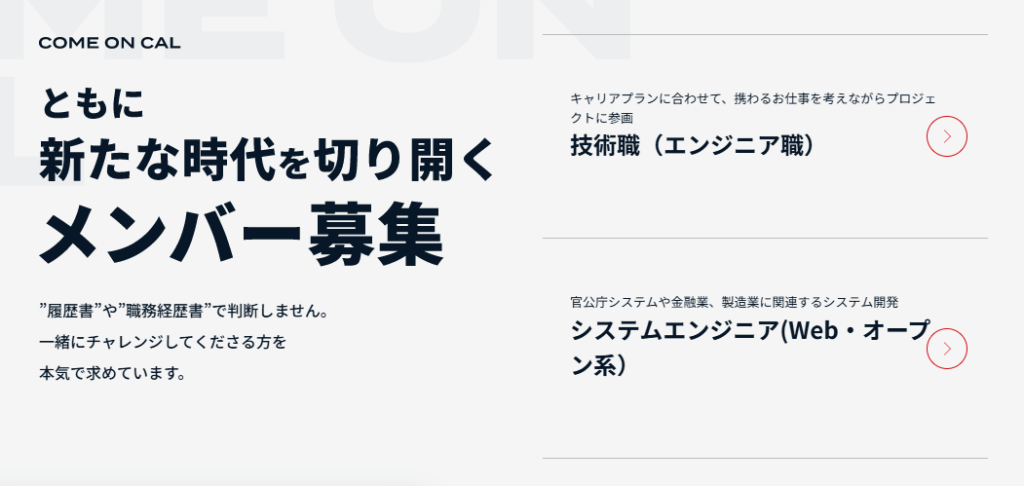みなさまこんにちは、キャル株式会社のけんけん(@cal_public)です。
派遣社員として働こうと考えている方の中には、自分に合った派遣会社の選び方がわからない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、すでに派遣社員として働いているものの、今の会社が自分に合っているのかわからない、相性が悪いから別の派遣会社に登録したい、と思っている方もおられるのではないでしょうか。
「派遣会社の選び方はどんな方法が正解なんだろう…」と迷ったら、まずは
- 自分に合う求人がきちんと届くか?
- 担当者と話が通じるか?
- 就業後も支えてくれるか?
この3点に絞ってみてください。
結論から言うと、派遣会社の選び方は一社完結で決め打ちしない方がうまくいきます。
最初に複数の派遣会社へ登録して、1〜2週間で比較し、担当者の質と求人の質を実体験で見極める。ここまでできれば、派遣会社選びで失敗することは防げます。
本記事では、検索意図に沿って「基本の比較軸」「面談での確認ポイント」「ケース別・条件別の派遣会社の選び方」まで、実務目線で解説しています。ぜひご一読ください。
最初に押さえる「派遣会社の選び方」の要点
まず全体像をそろえましょう。
結論、派遣会社の選び方はシンプルです。求人は数だけでなく質で見る、担当者は相性だけでなく提案力で見る、そして就業後のフォローは連絡の速さだけでなくルールの明確さで見る。
これを短い期間で体験し比較することで、派遣会社の選び方は自然と定まります。
今回は、派遣会社の選び方の比較軸を最初に共有して、登録〜面談でどう聞けば良いか、顔合わせの前に何をすり合わせればミスマッチを防げるかを、順番にお伝えします。
- 未経験で事務に挑戦したい方
- 製造・軽作業を安定して稼働したい方
- IT・クリエイティブで単価とスキルの両方を上げたい方
それぞれに合う派遣会社の選び方も具体例で示します。
読み進めるほど、あなたの中でこれが自分の派遣会社の選び方だという物差しができてくるでしょう。
派遣会社の選び方の基本軸
最初の面談で全部を見抜くのは難しいのですが、派遣会社の選び方の軸がわかっていると迷うことは少なくなるでしょう。
ここでは「求人の数と質」「担当者の専門性と伴走力」「福利厚生と就業後サポート」という3つの柱で、派遣会社の選び方を解説します。参考にしてください。
求人の「数と質」(自分の職種・地域・希望条件にどれだけ合うか)
派遣会社の選び方で一番見落としがちなのが、求人数の先にある求人の質です。
公開求人が多く見えても、あなたの職種・地域・勤務時間・開始時期に合っていなければ意味がありません。面談では遠慮なく、「直近30日で、私の条件に合う新着の求人は何件くらい流れてきましたか」「この地域でフルタイムと時短の比率はどのくらいですか」のように自分が求める条件について詳しく聞きましょう。数字で返してくれる会社は、普段から案件の棚卸しができているサインです。
また、派遣会社の選び方では「募集背景」を聞くと求人の質が見極めやすいです。
- 欠員補充なのか
- 増員なのか
- 繁忙の波で短期なのか
- 定常の補完なのか
派遣先企業の事情が語れる会社は配属先と太く密接な関係を持っている可能性が高く、情報の信頼性が高いと言えるでしょう。
求人票では見えない実務の中身や残業の実態を一次情報として持っているかどうかが、派遣会社の選び方の重要な分岐になります。
専門性と担当者の質(業界知識・提案力・フォロー体制の実力)
派遣会社の選び方で決め手になるのは、担当者の聞く力と翻訳する力です。
あなたの職務経歴や希望条件を、派遣先の評価基準に合わせて言い換え、強みを定量で整理してくれるかどうかです。
例えば、事務なら処理件数や平均処理時間、製造なら歩留まりや不良率、ITなら使用ツールや担当フェーズといった、評価の物差しにあわせて話しをしてくれる担当者は信頼できます。
もう一つ、派遣会社の選び方で見たいのが、顔合わせ前の準備の伴走です。
想定質問のリストや逆質問の例、職務要約の書き直し、オンライン接続の事前チェックまで段取りを組んでくれる会社は、配属後のフォローも手厚い傾向があります。
担当者が忙しそうなら、その体制でも大丈夫か、サブ担当やコールセンターの応答時間はどうか、というようにサポート体制を先に確認しておくと、派遣会社を選んでから後悔しません。
福利厚生・就業後サポート:健康診断・有休・教育支援・トラブル時の対応
福利厚生は“あれば安心”ではなく、派遣会社の選び方の核心とも言えます。
定期健康診断や有休の取りやすさ、社会保険の加入条件、交通費や在宅手当の扱い、eラーニングや資格支援の有無まで、最初の面談で具体的に確認しましょう。教育支援が充実している派遣会社の選び方は、未経験→実務の橋渡しに効きます。
また、トラブル対応も重要な要素です。
ハラスメントや不適切な質問があった場合の相談窓口、就業先との認識齟齬が出たときの是正フロー、契約更新・満了時の連絡タイミング、これらを運用の手順で説明できる会社は、派遣会社として安心度が高いと言えるでしょう。
派遣会社の選び方チェックポイント(面談・登録時)
いよいよ登録・面談の場面です。
ここでは、派遣会社の選び方で迷わないように、当日の会話で使える聞き方に落として解説します。大切なのは、あなたの希望をただ伝えるだけでなく、派遣会社の一次情報を引き出すことです。
登録〜面談で聞くこと(募集背景/配属先の体制/残業・シフト・評価指標)
面談の序盤は、求人票の復唱に時間を使いがちですが、派遣会社の選び方では募集背景の方が価値があります。
「この募集は欠員ですか、増員ですか」「配属部署の人数と年齢構成、男女比、繁忙の季節性はありますか」のような逆質問に加え、「残業は『何時間までOKか』ではなく『平均は何時間か』『波はどこで強いか』」と、実態を数字で聞くようにしましょう。
評価指標も同様です。事務なら正確性や処理件数、製造なら安全と品質、ITならスプリントのバーンダウンなど、派遣先が何で評価をするのかが分かると、派遣会社選びとその先の働き方の解像度がぐっと上がります。
顔合わせ前のすり合わせ(就業条件のズレ防止と情報の出し方)
顔合わせは面接ではありません。しかし、顔合わせの方法は派遣会社を選ぶ際の重要な要素の一つです。
担当者と一緒に、職務要約を業務×役割×成果×ツールの順で1段落にまとめ、想定質問に対する答えを短文化しておきましょう。勤務時間や通院、家庭都合など、配慮が必要な事情は、言い方を工夫しつつ事前に派遣会社経由で共有します。
ここでの段取りが滑らかだと、当日の印象は安定しますし、派遣会社の選び方としても伴走力の有無がはっきり見えます。
口コミ・評判の読み方(サンプル偏りと一次情報の取り方)
口コミは参考になりますが、派遣会社の選び方では偏りに注意が必要です。
口コミの特徴として、悪い体験は目立ちやすく、良い体験は言語化されにくいものです。
そこで、評価を見るときは、職種・地域・勤務形態が自分と近いものだけに絞って比較し、最終判断は面談での一次情報に寄せます。
担当者が求人票に書かれていない現場の温度を語れるかどうか、これが派遣会社の選び方の最終確認になります。
あなたに合う派遣会社の選び方
「派遣会社の選び方」は人によって正解が変わります。
未経験で事務に挑戦したいのか、シフトを安定させたいのか、業種は製造・軽作業なのか、単価やスキルを上げたいのか、業界はITなのか、クリエイティブ職を目指したいのかなど、ゴールが違えば見るべき比較軸も変わります。
ここではケースごとに面談でどう確かめ、どこに線を引けばいいかを整理します。
未経験・事務系志望の方(研修と案件母数を重視する選び方)
未経験の方が事務職に進むなら、派遣会社の選び方は「研修の実効性」と「案件の母数」を重視すると良いでしょう。
まず、Excelの使い方などのPC基礎やビジネスマナーの研修が、いつ・どれくらい・どの形式で受けられるかを具体的に聞いてみましょう。
動画研修だけなのか、演習つきの実地なのか、受講後にどの求人へ優先的に推薦してくれるのか、ここがぼんやりしている会社は就業までの導線が弱い可能性があるので注意が必要です。
次に、あなたの今の等身大で通る案件がどれだけあるかを確かめましょう。
総務・営業事務・データ入力・受付のどれが入り口として現実的か、直近30日の成約例をいくつか出してもらい、経験年数やスキル要件と照らし合わせます。
派遣会社の選び方としては、未経験可の入口案件を押さえつつ、半年後に狙える次の階段も同時に描いてくれる会社が安心です。顔合わせ前は、職務経歴書の書き直しと、オンライン接続の事前テストまで伴走してもらいましょう。
ここまでやってくれる担当者は、就業後の相談にも反応が早いことが多いです。
製造・軽作業志望の方(安全教育・送迎・シフトの安定性で選ぶ)
製造や軽作業を希望するなら、派遣会社の選び方の第一条件は「安全と安定」です。
安全教育は座学だけでなく、実機に触れるオリエンテーションがあるか、配属前に危険予知(KY)の訓練があるか、保護具の支給や費用負担はどうなるか、これらを面談で具体的に確認しましょう。
次に、送迎など通勤サポートの有無です。
地方や郊外の現場は、送迎バスの有無や駐車場を無料で利用可能か否かで、通える・通えないが決まります。送迎の出発地や時刻表まで共有してくれる会社は、現場との連携がしっかりできているサインです。
シフトの安定性も大切で、日勤固定なのか、2交替・3交替なのか、繁忙の波はどの月に来やすいのか、派遣会社を選ぶ際には、残業の平均時間や想定外の呼び出しの有無・頻度まで数字で語れる会社を選ぶと、生活のリズムが崩れにくくなるでしょう。
最後に、評価の物差しです。
不良率、歩留まり、タクトタイム、出勤率など、現場で見られる指標を担当者が言葉にできるか、ここが言えれば契約更新や時給アップの打ち手も早くなります。安全第一で続けたい方は、派遣会社の選び方を教育+導線+波の見える化で決めると良いでしょう。
IT・クリエイティブ志望の方(技術スタックと単価の透明性で選ぶ)
IT・クリエイティブ領域で派遣会社を選ぶ際には技術の言語化ができるかを重視しましょう。
あなたが触れる予定の言語・ツール・デザイン環境・クラウド基盤が、案件票の言葉としてどれだけ具体的かを見ます。
「Web系」「社内SE」「デザイン補助」といった曖昧な括りだけだと、実務に入ってからズレが生じやすいので、React/Vue、Java/Go、Figma/AfterEffects、AWS/GCPといった固有名詞まで落ちているかを確認し、担当者が詳細を把握できているか質問しましょう。
また、単価の透明性も外せません。
時間単価、精算幅、残業の計算方法、リモートの可否、支給PCのスペック、リソース管理・チケット運用・デプロイ手順など、現場の運用が具体的に語られるかが、派遣会社の選び方の着目点です。
可能なら、同種案件の直近の単価相場や、半年後に単価アップを狙うための見せ方も合わせて相談します。
技術面談がある案件では、事前の模擬質問と職務要約のチューニングにどれだけ時間を割いてくれるかが、その派遣会社の伴走力を測る指標になります。ここが手厚い会社は、契約更新の交渉でも心強いと言えるでしょう。
働き方に合わせた派遣会社の選び方
「何をやるか」と同じくらい、「どう働きたいか」も派遣会社の選び方には重要です。
時短や在宅、地域の事情、紹介予定派遣の有無など、あなたのライフスタイルにあわせて確認すべき観点を先に言葉でそろえておきましょう。
時短・フレックス・在宅希望(柔軟な就業規則と実績を見極める)
時短やフレックス、在宅を前提にするなら、派遣会社の選び方は規則と実績の二本柱で判断します。
まず、就業先の規則として認められているのか、部署単位の裁量なのかを切り分けます。社内規定で在宅は週2まで、時短は10:00–16:00を必ず含むといった条件がある場合、最初から案件を絞らないと後で無理が出ます。
実績はもっと重要です。
同条件で就業中の人が何名いるか、定着率はどうか、過去のトラブル事例と対処法は何だったか、ここまで答えられる会社は、内部の連絡線が整っていて派遣会社の選び方として信頼できます。
顔合わせ前は、在宅環境(回線速度・PC・セキュリティ)と勤怠の取り扱いを、派遣会社経由で先に握っておくとスムーズです。
首都圏/地方/リゾート(拠点網と地域密着の差で選ぶ)
地域で比べるなら、派遣会社の選び方は拠点網と地場の強さが決め手です。
首都圏は案件の母数が多い分、競争も激しいので、担当者のレスポンスと推薦スピードがモノを言います。地方は派遣先との距離感が勝負で、工場や物流センター、地場の大手企業と長く付き合っている会社が有利です。リゾート系は季節波動が大きいので、住み込み・寮・交通の手当、ピーク後の次案件へのブリッジまで含めて提案してくれるかで、派遣会社の選び方が変わります。
いずれも、面談の場でこの地域の強い派遣先トップ3を聞いてみてください。即答できる会社はデータが回っており、ミスマッチが少ない傾向です。
紹介予定派遣の狙い方(直接雇用前提の進め方と注意点)
紹介予定派遣を狙うなら、派遣会社の選び方は見極めと準備が肝です。
選考が二段階になるため、履歴書・職務経歴書・面接対策が通常の派遣より重要になります。ここをいつ・誰が・どこまで伴走してくれるかを、最初の面談で確かめましょう。
また、直接雇用後の処遇や評価制度、残業・固定残業の扱い、賞与や昇給のルールなど、先の条件をどこまで事前に開示してもらえるかでも、派遣会社の選び方は変わります。
合格可能性の見立てを率直に共有してくれる担当者と組むと、応募の順番やポートフォリオの磨き方が無駄になりません。
紹介予定派遣の雇用形態や特徴などの詳細は「【2025年版】紹介予定派遣とは?通常の人材派遣との違いや仕組みや正社員化のコツをわかりやすく解説!紹介予定派遣のメリット・デメリットもあわせて解説!!」で解説しています。ご参考になさってください。
派遣会社の選び方で失敗しないための進め方
ここからは、今日からそのまま動ける順番で派遣会社の選び方を仕上げます。
結論はシンプルで、複数登録で比較の物差しを作り、1〜2週間で案件を見比べ、配属後30日で振り返る。この3つを回すだけで、派遣会社の選び方はブレません。
複数登録→初回面談で基準表作成(比較の物差しを先に作る)
派遣会社選びで失敗しないための最初の一歩は、派遣会社を一社で決め打ちしないことです。
2〜3社に登録して、同じ条件(職種・地域・勤務時間・開始時期)で初回面談に入ります。その場で担当者に数字で答えてもらい、基準表を作りましょう。
例えば、「直近30日の新着案件数」「未経験OKの割合」「在宅・時短の実績」「平均残業時間」「募集背景(欠員/増員)」「配属先の体制(人数・年齢構成・波)」の6項目を、面談のメモ欄に同じフォーマットで並べます。
数字で返してくれる会社ほど、一次情報が強いので、派遣会社を選ぶ際の信頼度が上がります。
面談では、求人票の読み上げで時間を使い切らないように注意しましょう。
派遣会社を選ぶ際は「募集背景や評価の物差し」を先に押さえます。事務なら処理件数と正確性、製造なら安全と品質、IT・クリエイティブなら担当フェーズと使用ツール。担当者が自分の言葉で説明できるかどうかで、伴走力が見えます。
ここで作った基準表が、以降の派遣会社の選び方のものさしになります。
7〜14日で案件比較→顔合わせ準備(書類・質問・逆質問を短文化)
次の一歩はスピードです。
登録から7〜14日は、毎日1回は担当者と情報を往復させ、届いた求人を基準表で機械的に比較します。ここで「なんとなく良さそうに」流されると、主観に寄ってしまい失敗します。数字と一次情報で比べて、質の差をはっきり出しましょう。
顔合わせが見えてきたら、派遣会社の選び方の核心である準備の伴走をチェックします。
職務要約は「業務×役割×成果×ツール」で1段落に短く整え、想定質問への答えは2〜3行でそろえると良いでしょう。
逆質問は「配属先の体制・評価基準・繁忙期の波・使用ツールのバージョン・OJTの有無」など、当日のミスマッチを防ぐものに絞ります。オンラインなら、名前表記・音声・カメラ・背景のチェックまで派遣会社経由でリハーサルをしておくと、印象が安定します。
準備が段取り化できている会社は、就業後のフォローも強いので、ここも派遣会社の選び方の判断材料にすると良いでしょう。
就業後30日レビュー(担当者へのフィードバックと条件見直し)
配属して終わりにしないのが、失敗しない派遣会社の選び方のコツです。
就業後30日で短いレビューを1本入れて、担当者に一次情報を戻します。業務の実態、残業の波、コミュニケーションの雰囲気、評価の物差し、気になった点…ここで良かった点も言語化しておくと、次の案件提案を受ける際の質が上がります。
もしギャップが大きいなら、担当替えや別案件の提案を依頼して構いません。派遣会社の選び方は、就業後の修正力まで含めて見る必要があるのです。
この30日レビューは、未経験やキャリアチェンジの方ほどよく効きます。
研修の受講可否や次に身につけたいスキル、在宅や時短の希望、通院や家庭都合の共有など、言いにくい条件ほど派遣会社経由で丁寧に出すと、現場との関係が安定します。
トラブルや不適切な質問があったときの相談窓口やエスカレーション手順も、ここで再確認しておくと安心です。派遣会社の選び方は、問題が起きたときにどれだけ早く正せるかで差が出ます。
派遣会社の選び方でトラブルを避けるための注意点
派遣会社の選び方で最後に効いてくるのは、もめない運び方を最初から決めておくことです。
- 条件のすり合わせ
- 契約更新・満了の段取り
- ハラスメント対応
この3つを選ぶ際の延長で言葉にしておくと、配属後の小さな火種が大きくならないでしょう。ここでは少しだけ形式ばって解説します。
条件の直接交渉は派遣会社経由に統一する
現場で上長に直接、「残業を減らしたい」や「在宅にしたい」と言いたくなる場面が出てくるかもしれません。ただ、派遣会社を選ぶ際の観点では、条件の交渉は派遣会社経由に一本化します。
その方が、合意の記録が残り、言いにくいことも角を立てずに通せるからです。
伝え方は短くて十分です。
例)「就業条件のご相談です。残業の上限を月10時間以内にしたいです。派遣会社から改めて正式にご連絡差し上げます」
この一言で、現場には相談の意志だけを共有し、調整は派遣会社が引き受けます。派遣会社を選ぶ際は、こうした橋渡しが上手い担当を選ぶかどうかが、配属後の安心に直結します。
担当が忙しく連絡が遅いと感じたら、「本文は私が下書きするので、会社名義で送ってください」と頼んでしまって大丈夫です。文章の骨子を自分で用意すると、処理は速くなります。
契約更新・満了・異動はカレンダー化して先に握る
更新や満了の連絡が直前になって慌てる…ここで消耗したくないと。
運用に落とす場合、最初の週に期日をカレンダー化しておくのがおすすめです。更新判断の社内期限、派遣会社への意思表示期限、派遣先連絡の予定日を、担当と一緒に目安日でいいので並べておきましょう。
言い回しは事務的で構いません。
更新希望のとき:「現行条件での更新を希望します。変更案があれば派遣会社経由でご提示ください」
条件調整が必要なとき:「更新は前向きです。開始時刻を9:30に、残業は月10時間以内に調整したいです(派遣会社から正式連絡します)」
満了のとき:「満了での終了を希望します。引き継ぎ計画は派遣会社経由で共有します」
このテンプレを担当と共有しておくと、派遣会社の選び方としての運びの強さが、日々の安心感に変わります。
異動の打診が来たときも同じで、仕事内容・勤務地・時間帯・期間の4点だけを先に数字で確認し、判断は派遣会社経由で返しましょう。
ハラスメント・不適切質問は即相談・即記録
嫌な質問や不適切な言動に遭遇したら、まず感情で反応しないことが大切です。
派遣会社を選ぶ際は、即相談・即記録をルールにします。時刻、場所、誰が、どんな言葉を、どの文脈で言ったか、感想ではなく言われた事実だけを箇条書きにして、当日中に担当へ共有しましょう。
例)「本日14:05、A課長から『結婚の予定は?』と質問を受けました。就業に関係しない内容と認識しています。今後の対応は派遣会社経由でお願いします」
この一通を送るだけで、状況は一気にコントロール下に入ります。必要があれば派遣会社が派遣先と調整し、再発防止の線引きをしてくれます。
派遣会社を選ぶ際は、こうしたときに早く・静かに・正確に動いてくれる担当かどうかを、登録時の段取りや説明の粒度で見極めることが重要です。相談窓口の連絡先と、代替担当のバックアップも最初に確認しておくと、気持ちがずっと楽になります。
小さなコツを積み重ねるだけで、配属後のストレスは驚くほど減ります。派遣会社は“入って終わり”ではありません。
交渉は会社経由、更新と満了は期日管理、トラブルは記録ベース、この3点を回すだけであなたの働きやすさは安定します。
続く章ではよくある質問(FAQ)に進み、登録数の目安や大手か中堅かといったお悩みに、派遣会社の選び方の視点で短く答えていきます。
派遣会社の選び方でよくある質問(FAQ)
「結局どう動けばいいの?」という声に、派遣会社の選び方の視点でサクッと答えていきます。
迷いどころは似ていますが、答えはいつも「数字と一次情報で判断すること」と「派遣会社経由で段取りすること」に戻ってきます。
大手と中堅、どちらがいい?(派遣会社の選び方の結論は相性×一次情報)
よく聞かれますが、派遣会社の選び方の結論は「どちらにも良さがあるので、相性で決める」です。
大手は案件の母数と拠点網が強く、初動の速さと選択肢の広さが魅力です。中堅は特定エリアや職種で深く、担当者が現場の温度をよく知っていることが多いです。
では、どう見極めるか。
登録〜面談で「直近30日の新着件数」「未経験OKの比率」「在宅・時短の実績」「募集背景の説明の粒度」を数字で出してもらい、派遣会社の選び方の基準表に並べましょう。同じ質問を複数社に当てれば、あなたに合う強みが自然に浮き上がります。
最後は担当者の伴走力、つまり職務要約の磨き込みや想定質問の準備をどこまで一緒にやってくれるかで決めると、大手でも中堅でも失敗しにくくなります。
何社まで登録していい?(派遣会社の選び方は2〜3社×1〜2週間が最短距離)
登録は2〜3社に絞るのが現実的です。
多すぎると連絡が分散して、選ぶ際の比較軸がぼやけます。期間は1〜2週間で集中して回し、毎日1回は担当者と情報を往復させましょう。同じ条件(職種・地域・勤務時間・開始時期)で面談に入り、数字で答えてもらった内容を基準表に追記していきます。
案件紹介が動き始めたら、顔合わせの準備に入る前に、派遣会社の選び方の視点で担当者の段取り力をチェックします。
職務要約を「業務×役割×成果×ツール」で1段落に短文化できるか、逆質問の質が上がる添削をしてくれるか、オンライン接続の事前テストまで並走してくれるか、ここまでそろえば登録社数を増やさずに決め切れます。
すぐに仕事が見つからないときの対処法は?(派遣会社の選び方の修正力)
焦る気持ちは当然ですが、派遣会社を選ぶ際は修正力が勝ち筋です。まず、基準表の数字を見直しましょう。
- 地域を一駅広げる
- 開始時期を2週間後ろにずらす
- 在宅の比率を下げる
- 時短なら曜日の固定を緩める
こうした微調整で一気に母数が増えることがあります。
次に、職務要約をアップデートします。
「前職の業務を成果とツールまで言語化しているか」「処理件数・平均処理時間・不良率などの数字を一つでも足せるか」を担当者と一緒に磨きます。それでも動かないなら、派遣会社の乗り換えも含めて見直しましょう。
返信が遅い、募集背景が曖昧、想定質問の準備に伴走してくれない、このあたりが続くようであれば別の担当・別の会社に切り替えるサインです。登録自体は無料なので、“比較してから決める”を貫いた方が、結果として早く決まります。
派遣会社の選び方をプロが解説!失敗しない比較基準と、タイプ別おすすめの選び方を徹底解説のまとめ
最後にもう一度、派遣会社の選び方の要点を短くまとめておきます。
見るべきは「求人の数と質」「担当者の専門性と伴走力」「福利厚生と就業後サポート」です。面談では募集背景・配属体制・評価指標・残業の波を数字で引き出し、顔合わせの前に「業務×役割×成果×ツール」で職務要約を1段落に整えます。
条件の交渉は派遣会社経由に統一し、更新・満了は期日管理、トラブルは即記録・即相談、これが崩れなければ配属後も安定します。
次の一歩はシンプルです。
今日のうちに2〜3社へオンライン登録を済ませ、同じ条件で初回面談を設定してみてください。面談の場で基準表を作り、7〜14日で案件を比較し、良い流れの会社と担当を一本化します。
ここまで運べば、あなたの派遣会社の選び方はもう勘ではありません。一次情報と段取りを味方にして、迷わず前に進みましょう。
キャルはITエンジニアを“育てる”人材派遣会社です!
キャルはWeb/オープン系・汎用系・制御組込系・インフラ系と、ITエンジニアの派遣に特化した派遣会社です。
- IT業界は初めてだけどチャレンジしたい
- 今までの経験やスキルを活かして新しいことに挑戦したい
- 派遣でも長期で安心して働ける職場を探している
- さまざまな経験を積んでスキルアップしながら働きたい
など、上記に当てはまる求職者や転職活動中の方は、一度キャルにご相談ください。
IT関連の求人が豊富なだけでなく、国家資格を持つキャリアコンサルタントによるフォロー、大阪府から委託を受けている関西最大級のIT人材育成訓練校「キャルITカレッジ」の運営など、エンジニア目線になった取り組みを多々おこなっています。
現在活躍中のエンジニアの中にはIT未経験だった者も多くおりますし、毎月入社組の同期がいるのも安心です。
一緒に働けることを心より楽しみにしています!
\エントリーはこちら/
キャルでITエンジニアに挑戦する