こんにちは、キャル株式会社のげんた(@genta_cal)です。
システムなどの受託開発を依頼したくても「メリットやデメリットは?」という不安や「依頼方法が分からない」という疑問を持つ企業さまも多いのではないでしょうか?
システム開発の依頼は、発注する企業にとって、社内に不足するIT人材やエンジニア不足の解消、コストや業務負担の削減、プロジェクトの品質向上など多くのメリットがあります。一方で、受注する企業側にも経験や実績の蓄積、新たなクライアント開拓などのメリットが存在するのです。
本記事では、受託開発の目的や契約形態、自社開発やSESとの違いを解説し、発注側・受注側それぞれの視点からメリットを紹介します。
「受託開発ってメリットあるの?」「うちの会社にはマッチしているのかな?」などの疑問をお持ちの企業さまはぜひご一読ください。
受託開発の目的や契約形態は?自社開発やSESとの違いも解説

「受託開発という言葉は聞いたことあるけど詳しく知らない…」という方のために、そもそも受託開発がどのようなサービスなのかや、自社開発やSESとの違いを解説します。
受託開発とは?
「受託開発」とは、システム開発やソフトウェア開発を外部の会社やエンジニアに委託し、成果物を納品してもらう仕組みです。
自社が発注し受注会社側にプロジェクト全体を受け持ってもらえる点が特徴で、要件定義・デザイン・実装・運用まで幅広い業務に対応してもらえます。
派遣や常駐のようにエンジニアを採用して社内で育成する必要はなく、外注としてノウハウやスキルを提供してもらい、工数の負担を軽減できる点が大きなメリットです。
クライアント企業は自社の事業目的に沿ったシステムを効率的に作成・完成でき、原因分析や改善を含めた高品質な成果物を得られる可能性があります。
なお、受注側には納期遵守や品質確保などの責任が求められます。受託開発は単なる外注ではなく、依頼する会社との信頼関係を前提とした業務委託であり、双方が経験やノウハウを共有しながら成功へと導く点も特徴と言えるでしょう。
自社開発との違い
受託開発と自社開発の大きな違いは、システムやソフトウェア開発を社内で完結させるか、外部の企業に委託するかという点にあります。
受託開発は他社に依頼する形態で、外部会社のノウハウを活用できるため、新規システム開発や大規模な案件にもスムーズに対応できます。
一方で自社開発は、自社のエンジニアがプロジェクトを進めるため、既存業務との連携や柔軟な対応が可能です。しかし、専門スキルを持つ人材が必要になることから、コストや時間の負担が大きくなります。
両者は同じ「開発」であっても目的や体制などの特徴が異なりますので、自社の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。
| 受託開発 | 自社開発 | |
| 開発主体 | 外部の専門企業に委託 | 社内のエンジニアが担当 |
| スキル確保 | 外部のノウハウを活用可能 | 自社で採用・育成が必要 |
| コスト | 契約時に定めた費用 | 社内での人件費が中心 |
| 対応範囲 | 新規開発や大規模案件に強い | 既存業務との連携 |
| 柔軟性 | 契約内容により異なる | 社内事情に即した運用 |
SESとの違い
受託開発とSES(システムエンジニアリングサービス)は、どちらも企業が自社のITプロジェクトを外部に依頼する方法ですが、その仕組みは大きく異なります。
受託開発は成果物の完成を目的として外部委託し、受注会社がプロジェクト全体を管理・運用し納品まで責任を持つ形態です。クライアント(発注側)は「完成品をもらう」ことに重点を置くことになるため、社内の管理負担を減らしつつプロジェクトを進行できます。
一方、SESはエンジニアを常駐させ、社内の指揮命令下で業務をおこなってもらう契約形態です。プロジェクト管理の責任は発注側にあり、成果物ではなく工数時間に対して費用が発生します。
要するに、受託開発は「成果物の納品」、SESは「リソースの提供」という目的の違いがあるため、目的や社内体制に応じたサービス形態を選ぶことが重要になります。
| 受注開発 | SES | |
| 契約対象 | 成果物(システムやソフトウェアなど) | エンジニアの工数 |
| 管理責任 | 受注企業側 | 発注企業側 |
| 作業場所 | 外部の受注企業 | 発注企業に常駐 |
| 契約目的 | 成果物の納品 | 人材の支援・工数確保 |
| 費用 | 成果物単位 | 作業時間単位 |
なお、SESの詳しい特徴やサービスについては、以下の記事で解説していますのでぜひご覧ください。
【参考記事】
「SES」の利用が向いている企業とは?SESの特徴やサービス概要、エンジニア派遣との違いを紹介。利用する際のメリット・デメリットとあわせ詳しく解説!
受託開発を発注する企業側のメリット

ここまでは、受託開発のサービスや特徴、自社開発やSESとの違いを解説しました。
次は、受託開発を発注する企業にとってのメリットを4つ紹介しますので、発注を検討している企業さまはぜひ参考にしてください。
メリット1.自社にIT部門がなくてもシステム開発が可能
一つ目のメリットは、自社にIT部門がなくてもシステム開発が可能である点です。
企業が新規のシステム開発を検討する際、社内にIT部門やシステムエンジニア(SE)が不足しているケースは少なくありません。
こうした状況では、外部の会社へ開発を委託することで、自社にリソースがなくても専門のエンジニアの技術を活用できます。
委託することで発注企業は、ITやプログラミングの知識がなくても、業務に必要なシステムをプロジェクトとして進められます。デザインや設計、エンジニアの業務調整も受託会社が対応してくれます。
期間も柔軟に設定でき事業のニーズや問題解決にも直結することから、社内に専門人材がいない企業には特におすすめです。
メリット2.開発工数やコスト削減につながる
二つ目のメリットは、開発工数やコスト削減につながる点です。
社内で開発やプロジェクトを進める場合、通常であればエンジニアや担当SEなど専門人材を確保する必要がありますが、専門の開発会社に外注・委託することで、必要な技術や体制をすぐに活用できます。
また、業務のピークや短期的な事業課題にも柔軟に対応できるなど効率的です。結果として、自社では限られたリソースを有効活用しながら、不足リソース分の採用コストを削減できるため、システム開発を効率的かつ円滑に進められるでしょう。
メリット3.豊富なスキルと経験を活用できる
三つ目のメリットは、豊富なスキルや経験を持つエンジニアの知識やノウハウを活用できることです。
自社だけでは導入が難しい最新技術や専門分野の技術力を持つ人材に依頼することで、開発の効率や品質を高められます。受託開発を展開している企業は幅広い実績を蓄積しており、課題に応じた最適な方法や対策を提案可能です。
また、多彩な能力を持つエンジニアを自社で採用・育成する必要がなく、外部の強みを活かしてシステムを進めることが可能になります。これによって、自社の課題解決や新たなビジネス機会につながる可能性も広がり、競争力強化も期待できます。
メリット4.追加開発も依頼できる場合がある
追加開発も依頼できる可能性がある点もメリットです。
システム導入後に新たに作業が必要な場合でも、受託契約であれば追加依頼できることがあります。また、費用を追加で支払うことで、段階的な拡張や改善を進められるケースもあります。
請負契約では当初の仕様を完成させることが目的のため、契約外の作業対応はしてもらえないことがほとんどです。
それを踏まえると、自社の成長や進捗具合に合わせてシステムを強化できる点は受託開発のメリットと言えるでしょう。
受託開発を受注する企業側のメリット

前項では受託開発を発注・依頼する企業側のメリットを紹介しましたが、もちろん受注する企業側にもメリットがあります。受注する企業のメリットは、発注する企業のメリットにもつながりますので、ぜひご確認ください。
メリット1.幅広い知識や技術が身につく
受託開発を受注する企業側のメリット一つ目は、さまざまな技術や知識が身につくことです。
受注した企業はさまざまな要件や機能に対応するため、受託案件を通じて設計や開発のスキル・知識が蓄積できます。
異なる環境での課題解決や対策を経験することで、エンジニアは高い技術力とノウハウを習得していけるでしょう。
この点は発注する企業にとっても大きなメリットです。
発注時には受注企業が培った豊富な経験や知識を活用できるため、問題の早期解決や品質向上につながります。幅広い技術力を持つ企業に依頼することで、システム開発の課題に的確に対応できる可能性が高まるでしょう。
メリット2.基本的には自社システムで開発可能
開発時に自社システムを活用できることもメリットと言えます。
受託開発では、受注企業のエンジニアが自社のシステムや社内の環境を活用して開発を進められるため、既存の技術や運用方法を組み合わせることで、業務効率を高めながら仕様変更が発生した際にも柔軟に対応可能です。
また、自社のノウハウを導入することでリスクを防ぎやすかったりします。
発注側にとっても、受注企業が自社に適した開発環境で進めることで、高品質な成果物を効率的に得られる点はメリットと言えるでしょう。
結果的にシステム導入や業務改善の効果を最大化できるため、受託開発は安心できる依頼方法と言えます。
メリット3.案件数が多く需要が絶えない
受注企業にとって、案件数が多く需要が絶えない点は大きなメリットと言えるでしょう。
受託開発は2024年から2025年にかけても市場規模が拡大しており、システムやアプリの開発ニーズは多岐にわたります。受注企業側から見ると、業界全体でクライアントからの依頼が絶えず、新規プロジェクトや下請け案件も含め安定的に仕事を確保できているわけです。
これはエンジニアのスキル向上や自社の技術蓄積にもつながり、長期的な成長基盤を築ける要因になります。
また、発注企業側から見ても、受注企業が多様な案件を持っていることで、さまざまな技術力や経験が蓄積されるため大きな利点と言えます。
実績がある開発力を活かせることで自社のシステム開発時に活用してもらえる他、システムの拡張や仕様変更の際にも技術を発揮してもらえるでしょう。
受託開発にはメリットだけでなくデメリットもある

ここまでは受注企業側におけるメリットを紹介しました。
続いては、受託開発を活用する際のデメリットを解説します。依頼後に「見当違いだった…」とならないように必ずチェックしておきましょう。
デメリット1.コミュニケーションが難しい
受託開発におけるデメリットの一つ目は、コミュニケーションの難しさです。
発注側と受注側がシステム要件を十分に擦り合わせないまま進めてしまうと、認識のズレからトラブルや失敗の可能性が高まります。そのためは、要件定義を明確におこなうことや、定期的にスケジュールや状況を確認することが大切です。
さらに、進捗報告や打ち合わせを重ねることで信頼関係を築き、適切な管理と対策を講じることが必要になります。
受託開発は効率的にプロジェクトを進められる反面、コミュニケーション不足が致命的なデメリットとなり得るため主体性を持って関与する姿勢が重要になってくるでしょう。
デメリット2.自社エンジニアの成長機会が減る
デメリットの二つ目は、自社エンジニアの成長機会が減るという点です。
外部に依頼すると計画や仕様などほとんどを委託先が担うため、自社のエンジニアは実務経験を積みにくく、スキル向上や新たな可能性を広げにくい事態が生じやすくなります。
その結果、長期的には企業の開発力に影響を及ぼすリスクもあるため注意が必要です。
とは言え、受託開発を活用しながら、自社でレビューや要件定義に関わる仕組みを整えることで経験を積んでいくことは可能です。工夫次第ではデメリットを抑えつつ成長機会を確保できるでしょう。
デメリット3.セキュリティリスクに注意が必要
デメリットの三つ目は、セキュリティリスクに注意が必要な点です。
発注側と受注側の環境や運用方法の違いから、情報漏洩や不正アクセスなどのトラブルが発生しやすくなる可能性があります。特に、自社の要望に合わせた設計段階での対策が不十分だと、重要な情報資産を守りにくくなってしまうでしょう。
そのため、契約時にはセキュリティ対策を徹底しているかを確認し、アクセス権限の管理や暗号化などセキュリティ要件を明確にすることが重要です。
セキュリティ面を軽視することは大きなリスクを伴いますので、発注企業としては万全な体制を整えたパートナー選びが必要となります。
受託開発を成功に導くポイントは「依頼する会社選びを失敗しないこと」

前項では受託開発のデメリットを紹介しました。
次は、受託開発を成功に導くポイントとも言える「依頼する会社選び」について解説します。
会社選びを失敗してしまうと、納期遅延や低品質などの問題が発生してしまう可能性もゼロではありません。
ここでは、会社選びのポイントと注意点を解説しますので、ぜひ確認しておいてください。
開発会社を選ぶ際のポイント3つ
受託開発を依頼する際、どの開発会社を選ぶかが、プロジェクトが成功するか否かを大きく左右します。
そのためには、以下3つのポイントを意識して開発会社を選ぶことが重要です。
開発会社の業界経験や実績
まず確認すべきは、開発会社の業界経験や実績です。
自社の目的に近いプロジェクトを手掛けた実績があるかどうかで、スムーズな対応や課題解決力に差が出ます。特殊なシステムではその分野に精通しているかが成功へのカギになります。
技術力や専門性
技術力や専門性もポイントです。
最新の開発手法やセキュリティ対策を徹底している会社であれば、将来的な拡張やトラブルを防げます。また、開発に必要なエンジニアが揃っているかどうかも見極めましょう。
コミュニケーション能力
フロントとなる担当者のコミュニケーション能力も軽視してはいけません。
こちら(発注側)の要望を正しく理解し、柔軟に対応できるか否かによって納品までの進行に大きな違いが発生します。そのため、定期的な報告やフィードバック体制が整っているかを確認する必要があります。
受託開発の会社選定は、経験・技術・コミュニケーションの3つを軸に選ぶのがポイントです。自社の目的に合った開発会社を選ぶことが成功への近道となり、安心してシステム開発を進められるでしょう。
開発会社を選ぶ際の注意点
開発会社の選定はプロジェクト成功に直結します。
万が一、注意点を押さえず闇雲に選んでしまうと、トラブルや失敗の原因となる可能性があるため、くれぐれも慎重におこなう必要があります。
開発会社の得意分野は必ず確認すること
開発会社の得意分野は必ず確認するようにしましょう。
業界やシステムの種類によって専門性は異なるため、自社の目的に合った分野で豊富な実績を持つ会社を選ばないと、損失につながってしまう恐れがあります。
自社と似たシステム開発経験の有無の確認を怠ってはいけない
自社と似たシステム開発経験の有無の確認も怠ってはいけません。
成功事例や課題対応の経験はリスク軽減にもつながります。そのため、いくら経験豊富な会社であっても、類似システムの開発経験がなければ仕様変更やトラブル対応が難しいケースがあるため、必ず確認するようにしましょう
運用・保守やアフターフォローの事前確認も怠ってはいけない
開発後の運用・保守やアフターフォローの事前確認も怠ってはいけません。
納品後に問題が発生した際の対応範囲や期間を明確にしておかないと、後々になって大きなトラブルに発展してしまう可能性もゼロではありません。プロジェクト後のトラブルを未然に防ぐためにも、アフターフォローの内容は事前に確認しておきましょう。
以上のポイントを踏まえ、開発会社を選ぶ際には得意分野・実績・アフターフォローの3点に注意することで、自社にとって最適な開発会社選びがおこなえるでしょう。
受託開発を依頼してから納品までの流れ
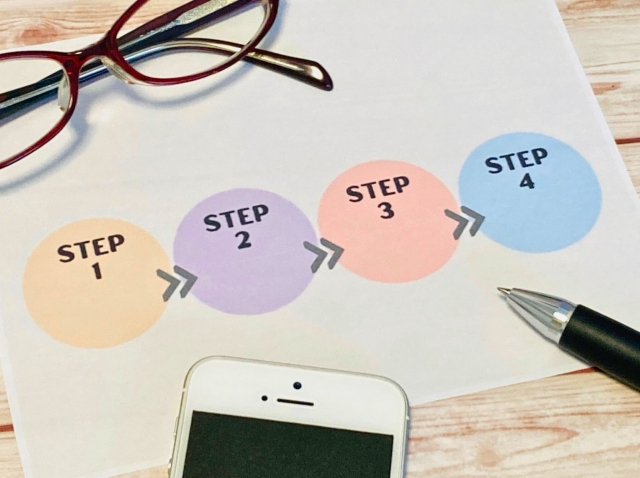
前項では開発会社選びのポイントや注意点を紹介しましたが、次は依頼してから納品までの流れを解説します。
1.提案依頼書の作成
受託開発を依頼するにあたって、まずは提案依頼書を作成しましょう。
自社が必要とするシステムの目的や要件を整理し、機能や仕様だけでなく、予算や納期などの条件も記載すると良いでしょう。
提案依頼書に明記しておくことで、後のトラブルや失敗を避け、スムーズなシステム開発につながります。
2.依頼会社の選定
提案依頼を基に複数の開発会社を比較検討します。受託開発では、得意分野や過去の開発実績を確認することが特に重要です。
自社と類似するシステムの実績があるか、担当者の対応力や技術力を見極めることで、開発後のトラブルを回避できます。また、契約後の運用・保守までサポートできるかも確認することがポイントです。
成功の鍵は「信頼できる開発会社選び」ですので、くれぐれも慎重におこなうようにしましょう。
3.見積り・契約の締結
依頼会社が決まったら、見積りの提示を受けて契約を締結します。
受託開発の契約では、納期や費用だけでなく仕様変更時の対応ルールや支払い条件を明確にしておくことが重要です。
契約内容を曖昧にすると後に失敗やトラブルの原因となるため、注意点を整理した上で合意形成を図りましょう。特に、アフターフォローや保守契約の範囲も契約段階で確認しておくと安心です。
4.開発の進行
契約を締結後、本格的なシステム開発が始まります。
受託開発では、要件定義から設計、プログラミング、テストまでの工程を開発会社が主体的に進めます。
発注企業は、定期的な打ち合わせや進捗報告を通じて状況を把握し、必要に応じて修正点をフィードバックすることが重要になります。このプロセスで双方のコミュニケーションが不足すると納品後のトラブルにつながるため、積極的に確認をおこなうようにしましょう。
5.納品・検収
開発が完了すると成果物が納品されます。
発注企業側は検収をおこないシステムが要件通りに動作しているかを確認します。
バグや不具合があれば修正依頼をおこない、最終的に問題なければ正式に納品完了です。受託開発では納品後の運用や保守フェーズも発生するため、契約時に取り決めたアフターフォロー体制を活用することが重要です。
適切な検収をおこなうことでトラブルを防げ、安心してシステムを利用できます。
受託開発のメリットに関するよくある質問6つ

前項では受託開発を依頼してから納品までの流れを解説しました。
最後は、受託開発のメリットに関するよくある質問を6つ紹介します。同じ様な疑問を抱いている方もいらっしゃると思うのでぜひ参考にしてください。
自社開発するよりもメリットある?
自社開発よりも受託によるシステム開発には多くのメリットがあります。
自社で人材や技術を抱える場合、採用や教育コストが高く成果物の完成まで時間がかかる点もリスクです。一方、受託では外部の企業に発注することで、既に蓄積された技術力や最新技術を活用でき、効率的にシステムを開発できます。
さらに専門家に任せることで品質に期待ができ、自社のリソースを本業へ集中させられるのも大きな強みです。企業にとっては短期間で高品質な成果物を得られる点で、自社開発以上の価値を感じられるケースが少なくありません。
受託開発がおすすめなのはどんなケース?
受託開発がおすすめなケースはさまざまあります。
一つ目は専門性が高いシステム開発が必要な場合です。自社に技術力がなくても、外部の開発会社に依頼することで高品質な成果物を得られる可能性が高まります。
二つ目は短期間で確実に成果を出したい場合で、得意分野の開発ノウハウを活かし効率的に対応してもらえるでしょう。さらに、自社リソースをコア業務に集中させたい場合にもおすすめで、システム開発を外部に委託することで本業やコア業務に注力できます。
人材採用や育成にかかる時間を削減できるって本当?
外部に開発を依頼することで、企業が自社で人材を採用し育成にかかる長期的なコストや人件費を大幅に削減できます。専門スキルを持つ外部パートナーに任せることで、開発を円滑かつ迅速に進められる点も大きなメリットと言えるでしょう。
特に新規事業や短期プロジェクトでは必要な成果物を効率的に得られるため、限られた予算や時間の中でも高い価値を実現可能です。結果として発注企業は人材確保に投じることなく、システム導入までのスピードを加速できます。
長期的なパートナーシップ構築につながるメリットはある?
受託開発の場合、長期的なパートナーシップ構築につながるメリットがあります。
理由としては、システム開発を一度きりの発注ではなく繰り返すことで、企業の業務や業界特有の課題を理解した上で改善提案や追加機能の計画を進められるケースが多いためです。
発注側・受注側双方の企業で継続的な体制を整えることで、長期的な信頼関係の構築が可能になります。結果として、企業側は将来的な開発ニーズにも柔軟に対応でき、安定した業務の運営や新規事業の推進にもつながるでしょう。
外注に依頼することで自社ではコア業務に集中できるの?
外注に依頼することで自社はコア業務に集中できます。
受託開発ではシステムやアプリの設計・開発などを外部企業に任せられるため、自社のリソースを本来注力すべき仕事に振り分けやすくなります。
例えば、マーケティングや新規事業の計画などに人材を充てられ、業務を円滑に進められるのが大きなメリットです。外注によって開発負担を軽減することで、企業は競争力強化や効率改善につなげられるケースも多くあります。
自社開発よりコスト削減につながりやすいのは本当?
自社開発よりも受託開発の方がコスト削減につながりやすいのは事実です。
理由は、システム開発に必要な人材を自社で採用・教育すると人件費や固定費の負担が高くなりやすく、予算を超えるリスクもあるためです。
受託開発では、外部企業に業務を委託することで必要な範囲に応じた費用を支払えば良いのです。そのため、高い専門性を持つ技術者に効率的に仕事を任せつつ、総額としてのコストを抑えられるケースが多かったりします。
受託開発のメリットに関する記事のまとめ
今回は、受託開発のメリットを中心に、受託開発の目的や契約形態、自社開発やSESとの違いを解説しました。
受託開発は、自社での内製化やSESと比較した場合、契約形態や目的が明確で企業のニーズに応じた柔軟な開発が可能です。
発注企業側にはコストや人件費の削減、専門性の活用、リソース最適化、納期の明確化といったメリットがあり、受注企業側にも安定した案件獲得や技術力向上の機会などが得られます。
ただし、要件定義の不一致や費用の増大などデメリットも存在するため、信頼できる開発会社を選ぶことが成功の鍵となります。
システム開発を外部委託する選択肢として、ぜひ受託開発をご検討ください。
キャルは受託開発も承ってます!
キャルは、官公庁さまとの25年以上の取引実績を基に、2017年より民間企業さまからの受託開発も開始いたしました。
銀行や物流業・製造業などと業界も幅広く、要件定義~テスト・運用、Web・オープン系や制御組込系と、あらゆる開発フェーズやシステム・ソフトウェアに対応しております。
- 新しいシステムを開発したいが人手不足
- 工数管理に時間を割かれるのが不安
- システム開発の経験者がいない
- ノウハウがなく開発できるのか心配
など、システム開発で不安を抱かれている企業さまは、ぜひキャルにご相談ください。
一括の大型システム開発からプロジェクト単位の開発と規模も問いません。
また、当社ではITエンジニアの派遣もおこなっております。
ご提案できる要員も常時100名程度と人材力には自信があり、課題解決に最適な人材を最短翌日にアサインすることも可能です。
すべての企業さまの事業を推進すべく、開発・人員の双方でサポートいたします。
\システム開発でお困りならご相談ください/
キャルの受託開発サービスを確認する

