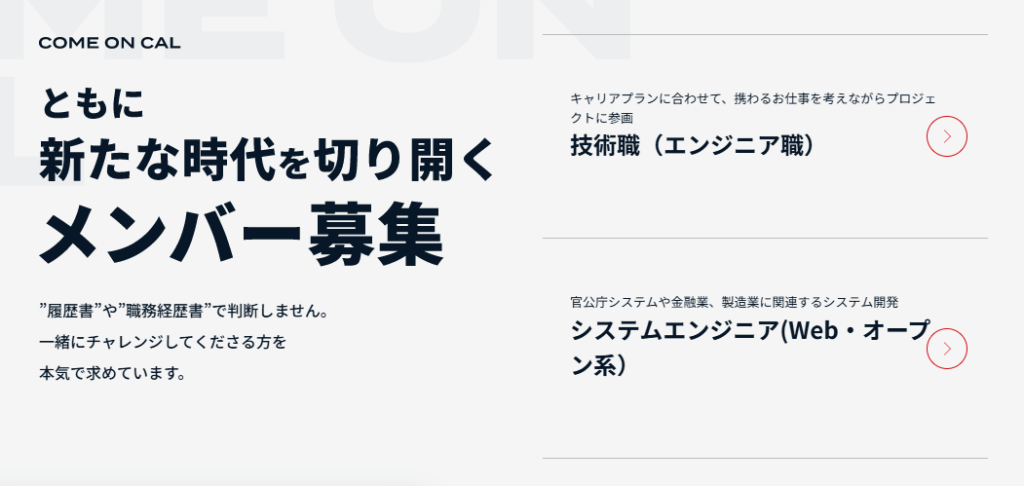こんにちは、キャル株式会社(@cal_public)のけんけんです。
「次の現場も案件ガチャになったらどうしよう…」そんな不安がよぎるなら、いったん立ち止まって仕組みを言葉でそろえましょう。
案件ガチャは偶然だけの話ではありません。配属の決まり方や事前情報の取り方、そして面談(顔合わせ)までの段取り次第で、当たり・ハズレの振れ幅は確実に狭められます。
本記事は、案件ガチャが起きる理由を構造から解きほぐし、SESと派遣の違いを3分で押さえ、今日からできる回避ステップと、派遣で働くことの魅力までを、ビジネス調の話し言葉でまっすぐお伝えします。
まずは用語と実態から一緒に整えていきましょう。
リード:結論と読み方
最初に結論からお伝えします。
案件ガチャは“完全な運”ではありません。配属プロセスの透明度と、あなたが取りにいく一次情報の質で、実はかなりコントロールできます。
特に派遣は就業条件の明示や事前説明の範囲が広く、条件・体制・評価の見える化をしやすいので、案件ガチャの振れ幅を小さくしやすい働き方です。
一方でSESは、契約と評価の筋が時間提供に寄りやすく、案件決定のタイミング次第で想像と違う現場に当たるリスクが残ります。
ここを理解しておくと、同じ案件ガチャでもどこまでが設計の話で、どこからが運なのかを分けて考えられるようになります。
本記事では
- 案件ガチャの実態
- SESと派遣の違い
- それぞれのメリット・デメリット
- 今日からできる回避手順
- 派遣で働くことの魅力
の順で案件ガチャについて解説し、回避策のご紹介を進めます。
必要なところだけ拾い読みしていただいて大丈夫ですので、ぜひご一読ください。
「案件ガチャ」とは何か(用語と実態)
「案件ガチャ」は、参加して初めて中身がわかるような配属を引き当ててしまい、希望やスキルと合わない現場に常駐することを、エンジニアの間で俗にそう呼んでいるだけです。
カプセル玩具のガチャになぞらえて、当たり・ハズレの不可視性を表しています。
実務では、炎上プロジェクトの応援に急きょ回される、単純運用の比率が想像以上に高い、就業条件や評価の物差しが曖昧なまま現場に入る、こうしたケースが案件ガチャの実感につながります。
なぜガチャと呼ばれるのか(配属の不確実性・情報非対称)
ガチャと感じる最大の理由は、配属の確定があなたの合意より先に進むことと、事前情報の粒度がそろわないことにあります。
営業都合のプッシュ、商流や時期の制約、スキル需給の偏りなどが重なると、面談前に本質情報を取り切れず、結果として案件ガチャに見舞われます。
定義としても、就労前後で待遇や中身のギャップが大きく、詳細が事前に判然としない状態が案件ガチャとされているのです。
ガチャが起こりやすい構造(商流・営業都合・スキルの需給ギャップ)
SESでは、お客さまの要望を受けて人材を素早くアサインする都合上、本人の適性と完全一致しないまま走り出すことがあります。
案件の内容や環境は千差万別で、単純作業に偏る、職場環境が合わない、評価が曖昧など、こうしたハズレの体験が案件ガチャの温床になります。逆に、要件が明快でチーム体制が整った“当たり”ももちろん存在しますが、そのばらつき自体が構造的リスクです。
どこまで運か、どこから設計か(コントロール可能領域を切り分ける)
運の領域はゼロにはなりません。ただ、募集背景、配属部署の体制、評価基準、繁忙の波、使用ツールとバージョン、稼働の上限と変動、こうした一次情報を数字で取りにいくことで、設計の領域は確実に広がります。
案件ガチャを避けるとは、この可視化を面談前後でやり切ることだと考えてください。本記事の後半で手順まで落とし込みます。
SESと派遣の違いを3分で(構造と配属の決まり方)
まず、言葉の定義をそろえます。
SES(システムエンジニアリングサービス)は、お客さまの現場に常駐し、時間を提供する契約(準委任)がベースです。派遣は労働者派遣契約で、就業条件や指揮命令系統が明示され、配属前の情報開示範囲も比較的広いのが一般的です。
どちらも現場で働く点は似ていますが、契約の筋と配属の決まり方が違います。
契約と評価の違い(準委任のSES/労働者派遣の派遣/成果と時間の扱い)
SESは「時間に対する対価」を基本に、稼働と作業範囲を現場で調整します。評価は役割を果たしたか稼働が安定したかなどプロセス寄りになりやすいです。
一方、派遣は就業条件と業務範囲が事前に定義されやすく、労務ルールや評価の物差しが可視化されやすいのが特徴です。
この違いが案件ガチャの体感差に直結します。
配属プロセスの違い(案件決定のタイミング・事前情報の粒度・顔合わせの役割)
SESは案件の波に合わせてスピーディにアサインされ、事前の粒度がケースバイケースになりがちです。派遣は、就業条件や配属体制の説明、顔合わせ前のすり合わせがプロセスとして定着しており、ここで疑問点を潰しやすくなります。
つまり、同じ案件ガチャでも、派遣のほうが未然防止のハンドルを握りやすい構造になっているのです。
案件ガチャの発生確率が変わるポイント(事前説明責任・就業条件の透明度)
派遣では、求人数や企業規模、サポート体制など、事前に比較できる材料が多く、会社ごとの得意領域も見えやすいです。面談時に募集背景や配属体制を数字で説明できるかを確かめるだけで、案件ガチャの確率はぐっと下がります。
一方、SES側で戦うなら、契約前に評価と範囲の線引きを文書化し、現場に入る前の期待値を合わせることが、最も効く打ち手です。
メリット・デメリットの要点(SES/派遣)
ここからは、意思決定に直結する実利で比較します。どちらを選んでも正解は作れますが、案件ガチャを避けたい視点で見ると、違いがよりクリアになります。
SESのメリット・デメリット(案件の幅・単価変動・裁量・ガチャリスクの大小)
メリットは、案件の幅を取りにいけることと、商流や時期が噛み合えば単価が伸びやすいこと。現場裁量が得られるプロジェクトに当たれば、短期間で成長カーブが立ち上がります。
デメリットは、案件決定のタイミングが速く、事前情報の粒度が安定しにくい点です。単純運用や補助的なロールに偏ると、スキル資産化の速度が落ち、案件ガチャの体感が強まります。
だからこそ、契約前の説明責任と、配属後の評価・範囲の明文化が鍵になります。
派遣のメリット・デメリット(条件明確・就業規則順守・異動調整・スキル成長の設計)
メリットは、就業条件や配属体制、更新や満了の運びが言語化されやすく、相談や異動の導線も確立していることです。教育支援や拠点網など、会社ごとの差も比較しやすいので、案件ガチャの見えない不安を減らしやすい働き方と言えます。
デメリットは、現場によって裁量や技術選定の自由度が限定されることです。ただし、評価の物差しやツールのバージョンを事前に確認できる分、スキル資産を積む計画は立てやすいのが実感としての強みになります。
どんな人に向くのか(志向・フェーズ・家計/生活リズムの観点)
短期間で幅を取りたい、商流とタイミングに張って高単価を狙いたいならSESのダイナミズムが合います。生活リズムの安定や条件の透明性、就業後の相談導線を重視するなら派遣が相性良しです。
いずれも、案件ガチャを避けるなら数字で一次情報を取り、文書化して合意するのが共通解です。
ここから先は、具体的な回避方法と手順、ケース別の動き方に踏み込みます。
なお、SESと派遣それぞれの特徴や違いについては「「SES」の利用が向いている企業とは?SESの特徴やサービス概要、エンジニア派遣との違いを紹介。利用する際のメリット・デメリットとあわせ詳しく解説!」で詳しく解説しています。あわせてご参考になさってください。
案件ガチャの回避方法(今日からできる実務)
ここからは、運ではなく設計で案件ガチャを避けるやり方に踏み込みます。
やることはシンプルで、事前情報を数字でそろえる→顔合わせを設計する→複数案件を同じ物差しで比べるの三段です。どれも今日から動けます。
事前情報の取り方:募集背景・体制・評価指標・波(繁忙)を数字で聞く
案件ガチャは、情報の粗さから起きます。そのため、最初の面談で担当者に数で答えてもらう質問を投げてください。会話の型は以下の通りです。
- 募集背景:「欠員補充ですか、増員ですか。直近3か月で同じ募集は何回出ましたか」
- 体制の見取り図:「配属部署の人数、役割の内訳、年齢レンジ、指揮命令の線はどうなりますか」
- 評価の物差し:「このポジションは何で評価されますか。例:チケット消化数、リードタイム、一次解決率など」
- 繁忙の波:「月間平均残業はどのくらいですか。繁忙期はいつで、最大どの程度まで伸びますか」
- ツールとバージョン:「Git/クラウド/設計ツールのバージョンは何を使っていますか。変更の裁量はありますか」
数字と固有名詞が返ってくるほど、案件ガチャは遠のきます。逆に「確認します」が続くなら、候補から一度外して問題ありません。
面談の最後に「ここまでの情報を文面で共有してください」と一言添えて、誤差を最小化しましょう。
顔合わせの準備:職務要約の短文化/想定質問と逆質問/オンライン接続の事前テスト
案件ガチャは、顔合わせの設計でさらに減らせます。職務要約は1段落・5〜7行でまとめ、順番は「業務→役割→成果(数字)→ツール/バージョン」で、例は以下の通りです。
例:バックエンド開発。注文管理の機能追加でAPI5本/スプリント2本を担当。平均リードタイムを28%短縮。Node.js18/NestJS/RDS(AuroraMySQL)/Terraform。レビューはペア+Lint/単体自動化(Jest)までを担当。
想定質問は「なぜこの案件なのか」「直近で詰まった問題と解き方」「苦手領域の扱い方」を2〜3行で用意し、逆質問は当日のミスマッチを防ぐ問いに絞ります。
例:「このポジションの最初の30日で期待される成果は何ですか」「任される範囲と相談の線はどこですか」「繁忙の波と残業の上限は合意できますか」
オンラインなら前日までに、氏名表記/マイク・カメラ/画面共有を5分でリハーサルしておきましょう。開幕の第一声と締めの一言まで決めておくと、印象のブレが消えます。ここまで段取りできれば、案件ガチャと呼ばれる偶然要素はだいぶ削れます。
複数社・複数案件の基準票比較:7〜14日で意思決定する手順
最後は比較の物差しを作ります。2〜3社・2〜4案件を、同じ表で並べます。
列は「募集背景/体制(人数・役割)/評価指標/ツール・バージョン/残業平均と波/在宅可否/時給・月給・交通費/開始時期/更新条件」です。
面談でもらった数字を埋め、空欄が多い案件は案件ガチャの温床になりやすいと判断しましょう。
運び方はこのリズムで十分です。
- Day1–3:登録・初回面談・一次情報の取得
- Day4–7:基準票に入力、1〜2案件を優先度順に絞る
- Day8–14:顔合わせ→合意事項を文面化→入場準備
決め切れないときは、KPIに効く実務がどれだけ担えるかで選びます。開発なら「どの機能を、どの指標で良くするか」、運用なら「どのSLAを、どう守るか」。ここが曖昧な案件ほど案件ガチャの振れ幅が大きいと心得ておけば、判断はぶれません。
ケース別:あなたならこう動く(再現性のある選び方)
同じ良い職場でも、人によって基準は変わります。そのため、案件ガチャを避けるには、あなたのフェーズごとに何を重く見るかを先に決めておくと早いです。
ここでは、未経験・若手、中堅〜リード、将来フリーランス志向の3パターンで、SESと派遣のどちらを軸にするか~案件ガチャを寄せ付けない動き方まで、会話の粒度で具体化します。
未経験・若手:教育導線と案件母数を重く見る/派遣で土台を固める
未経験や実務1〜2年目なら、まず学び続けられる場を外さないことが案件ガチャ回避の近道です。肩に力を入れず、教育導線と案件母数を最優先にしてください。
派遣を軸に置くと、就業条件や評価の物差しが見えやすく、案件ガチャの振れ幅を小さくできます。
登録時はこう聞きます。「未経験可の新着は直近30日で何件くらいか」「OJTの有無と担当者は誰か」「配属部署の人数と年齢レンジはどうか」です。
数字で返ってくる会社は、一次情報の精度が高いので、その分だけ案件ガチャが遠のきます。
SESで攻めたい場合も、教育の手当とレビュー体制の事実を先に押さえます。
聞くのは「レビューは誰がどの頻度で」「タスクの粒度は誰が切るか」「改善提案は拾われるのか」です。これが曖昧なまま走ると、簡単作業に固定されるハズレの案件ガチャに巻き込まれやすくなります。
最後に、職務要約は業務→役割→成果→ツールの1段落で固定しましょう。
「問い合わせ1次解決率を3か月で+12pt」「日報自動化で担当AHTを18%短縮」など、小さな成果でも数字を必ず添えることが重要です。この言い切り方が、案件ガチャの原因になる評価の曖昧さを前もって潰します。
中堅〜リード:技術スタックと役割裁量で選ぶ/派遣×紹介予定の狙い方
実装も設計も回せる中堅、あるいはリードを任される立場なら、案件ガチャ対策は役割裁量とアーキテクチャの自由度に集約します。ここを外すと、経験年数に見合わない運用系の雑務に偏って消耗します。
具体的には、「誰が決める側なのか」「技術選定の線引きはどこか」「レビューの基準と承認フローはどうか」を先に明文化させましょう。SESであっても、ここが文書で握れるなら、案件ガチャの確率は一気に下がります。
派遣なら紹介予定派遣のルートも現実的です。配属前に評価軸と処遇の見通しを握りやすく、案件ガチャに振り回されにくいです。
顔合わせでは「最初の30日・90日で期待される成果」「担当領域の境界」「スプリントの意思決定の場に入れるか」を短く確認し、OKなら迷わず進みましょう。ここで曖昧なら、基準票の裁量欄に×を付けて別の案件に切り替えます。意思決定を先延ばしにしないこと自体が、案件ガチャ対策になります。
将来フリーランス志向:ガチャを避けつつ売れる実績を積む動線
将来フリーを見据えるなら、案件ガチャを避けるだけでなく、売れる実績の積み方を逆算します。狙いは、指標で語れる改善と、道具立て(CI/CD・IaC・監視・SLA運用)の経験です。
SESを選ぶなら、案件選定の基準に「改善KPI」と「自動化の範囲」を入れてください。派遣を選ぶなら、就業条件の透明性を活かして成果のログを毎週残すクセをつけます。
また、簡単で構いませんので、「担当機能/前→後の数値/使ったツール/関与の深さ」をNotionでもスプレッドシートでも記録しておきましょう。これが次の提案や単価交渉で効いて、案件ガチャの起こりやすい情報非対称を自力で潰していけます。
もう一歩踏み込むなら、紹介予定派遣で正社員化の見取り図を確かめながら、設計〜運用までの一連を通して経験し、のちにSESや業務委託で横展開する方法もあります。
いずれにしても、案件ガチャを運だと諦めないことです。基準票で比較し、合意を文書にし、成果を数字で残す、これだけで将来の選択肢は増えていきます。
失敗パターンとリカバリー
「これはハズレ案件ガチャを引いたかもしれない」と感じたとき、やってはいけないのは我慢して時間を流すことです。
SESでも派遣でも、初動の3〜10営業日で打てる手は思っているより多いです。
ここでは、よくあるつまずき方を先に言語化し、同じ状況に入っても冷静に切り返せるようにしておきます。
ポイントは、事実を集めて一次情報で語ること、連絡線を会社経由に一本化すること、そして期限を決めて検証することです。この3つだけで、案件ガチャのハズレ感はかなり和らぎます。
「聞かなかった」が原因のミスマッチ(配属体制・評価軸・残業の波)
いちばん多い失敗は、面談や顔合わせのときに聞けなかったことが、配属後に重くのしかかるパターンです。
体制が想像より小さくて属人化していた、評価指標が明示されておらず成果が見えない、繁忙の波が強く残業が慢性化しているなど、こうしたズレは案件ガチャの典型的な引き金になります。
リカバリーは、まず最初の1週間で事実のログを作るところから始めます。短い箇条書きで構いませんので、誰が何の役割で、どの指示がどのチャネルから来て、あなたは何を何時間で処理し、どんな阻害要因があったかを、主観を挟まずに書き出してみましょう。
ログが溜まったら、派遣なら担当営業、SESなら自社のアサイン担当へ会社経由で共有します。伝え方は落ち着いて、こう言い切ると良いです。
「当初共有の体制図と実態に差があります。現在は実質2名体制で、レビューが滞留し、成果の可視化が難しい状況です。30日で改善できる打ち手を3点提案します。1.レビュー時間帯の固定、2.評価指標の簡易版(例:チケット消化と一次解決率)の合意、3.残業上限の目安設定。派遣先(またはお客さま先)には貴社経由でご連絡ください」
この一通で、あなたは感想ではなく設計の話をしています。案件ガチャに見える状況でも、一次情報と具体案をセットにすると、軌道修正のテーブルにつきやすくなります。
早期撤退の手順と次の当たりを引く準備(言い回し・連絡線・記録)
どう調整しても改善の見込みが薄いと判断したら、早い段階で撤退の手順に切り替えます。
ここでの肝は、感情で動かず、会社経由で段取りすることです。直接現場に伝えるのではなく、派遣なら営業、SESなら自社の責任者に、記録が残る形で要望を出します。言い回しは事務的で十分です。
「現場運用の前提と乖離が大きく、当初合意の条件(評価指標・残業・体制)が満たせていません。円滑な契約満了・撤退に向け、引き継ぎ計画と時期のご提案をお願いします。次案件では、事前に体制図と評価指標の文書合意を前提にさせてください」
撤退を決めた段階で、同時に次の当たりを引く準備も始めましょう。基準票(募集背景・体制・評価軸・残業の波・ツールとバージョン)を最新化し、案件ガチャの原因になった項目を、次回の必須質問に昇格させます。
派遣であれSESであれ、退く際の清潔さと次の要件定義の精度が、その後の紹介スピードとマッチ度を大きく左右します。
メンタルと学習の立て直し方(短期で成果を可視化する)
ハズレたかもしれないと感じると、どうしても自信が削られます。
しかし、ここを放置すると案件ガチャの連鎖を招きます。対策はシンプルで、短期で可視化できる成果を意図的に作ることです。派遣でもSESでも有効です。
例えば、手元のタスクに「小さなKPI」を置きます。
エラー調査の一次切り分け時間を自分の中で20%短縮する、日々のチケットに再現手順と原因を1行で添える、定期作業をスクリプト化して10分の短縮を積む。小さくても数字で語れる改善が増えるほど、職務要約の厚みが変わり、次の案件で当たりを引く確率が上がります。
もう一つは、週1で振り返りメモを残すことです。
事実(何をやったか)、気づき(次はどうするか)、依頼(会社に何を頼むか)をそれぞれ2〜3行で十分ですので、派遣なら担当営業、SESならアサイン担当に共有しておくと、あなたの修正力が見える化され、次の提案の質が上がります。案件ガチャが怖くなくなるのは、こうした小さな設計を積み上げた後です。
派遣で働くことの魅力(案件ガチャを避けたい人へ)
ここからは、案件ガチャの振れ幅を小さくしたいという人に、派遣という働き方の良さを実務の言葉でお伝えします。
派遣は、就業条件や配属体制の事前開示が厚いぶん、入場前にズレを潰しやすい構造になっています。
面談や顔合わせの前後で、募集背景・配属体制・評価指標・繁忙の波・残業上限・ツールのバージョンまでを数字で握ることができるので、いわゆる案件ガチャの中身が見えない怖さをかなり減らせるでしょう。
加えて、就業後の相談窓口と異動の導線が整っている会社を選べば、もしズレが出ても会社経由で静かに修正可能です。
結果として、仕事内容・時間・場所・評価の4点が安定しやすく、日々が設計できるリズムに変わります。
条件の透明性と運用の安定(就業条件・相談窓口・更新手順)
派遣の強みは、言い換えると見える化×手順化です。
就業条件は書面で固まりやすく、勤務時間、休憩、残業の扱い、在宅可否、セキュリティのルール、評価の物差しまでが事前にすり合わされます。
顔合わせに入る前に担当者と「最初の30日で何をもって合格とするか」を一文で握っておくと、案件ガチャの核心である評価の曖昧さが解消されます。就業後にギャップが出たとしても、派遣会社の相談窓口とエスカレーションの線が用意されているので、現場に直接ぶつからずに温度調整が可能です。
更新や満了の手順も最初にカレンダー化できるため、直前の突然の依頼に振り回されにくい。こうした運用の安定が、メンタルの消耗を減らし、案件ガチャをたまに起こる例外に押し込めます。
例えば、入場前に「平均残業は月10時間前後、繁忙期は最大20時間まで。評価はチケット消化数と一次解決率で見る。在宅は週2日で固定」という合意を紙に落としておくことで、現場の温度が上がっても合意に戻るだけで会話が終わります。
派遣ならこの戻れる紙を最初から作りやすいので、案件ガチャに引きずられない日常が作れます。
スキル資産の積み上げ方(職務要約×数値成果×ツールのバージョン)
もう一つの魅力は、スキル資産の積み上げが計画しやすいことです。
派遣は、配属前に使用ツール・バージョン・担当範囲が見えやすいので、半年の学習計画と職務要約の更新計画を最初に描けます。案件ガチャを避ける要領で、週次・月次の成果ログを軽く回してください。書き方はシンプルで十分です。
「担当:受注APIの改修/2スプリントで5本」「成果:平均応答時間を1.8秒→1.2秒」「根拠:p95計測・リグレッションテストのスクショ」「ツール:Node.js18/NestJS/AuroraMySQL/GitHubActions」
「運用:インシデント初動を30分→15分」「SLA:S1初動15分以内を4週連続で遵守」「自動化:ジョブ再実行の手順を整備、手戻りゼロ」
この業務→役割→数字→ツールの一段落を積むほど、次の案件選定であなたが案件ガチャを起こしにくい人材になります。なぜなら、派遣会社が求める再現可能な実績が、すでにあなたの手元に並ぶからです。
派遣は評価の物差しが定義されやすいので、数字を乗せやすい面があります。つまり、案件ガチャを避けたい人ほど、派遣の数字で語れる日常が相性良いのです。
紹介予定派遣という選択肢(直接雇用までの見通し)
さらに、紹介予定派遣を選ぶことで、派遣の透明性と直接雇用の安定を橋渡しできます。
はじめから正社員化の見取り図が言葉になりやすく、試用期間の扱い、年収レンジ、等級や評価のフレーム、配属後のキャリアパスなど、将来の景色が描けるでしょう。
面談では「30日・90日で期待される成果」「担当領域の境界」「技術選定や改善提案の通り方」を短く確認し、紙で握って入るだけで、案件ガチャの余白はぐっと縮みます。
あわないと感じたら、派遣会社経由で静かに軌道修正できるのも、紹介予定派遣の取り回しの良さです。
紹介予定派遣のもう一つの効能は、売れる実績の作りやすさにあります。
正社員前提の現場は、評価とKPIが比較的整っているため、あなたの数字の履歴がきれいに並びます。半年後にSESやフリーランスへ展開したいと考えている人にとっても、この数字の履歴は案件ガチャを避ける“最強の防具”になるのです。
派遣の良さは、条件と運用の透明性、修正の手順化、そして成果の数値化です。これらはすべて、案件ガチャの原因である情報非対称と評価の曖昧さを削るための装置でもあります。
就業前に数字で合意し、就業後は会社経由で修正し、成果は一段落で数字に落とす、たったこれだけで働き方のストレスは驚くほど減ります。
よくある質問(FAQ)
「ここがまだモヤモヤする」という点について、案件ガチャの観点でスパッと言い切ります。
結論はいつも、一次情報を数字で取りにいくことと、合意は文面に落とすことです。
派遣とSESを両方登録するのはアリか?
アリです。というより、案件ガチャを避けたいなら合理的です。
同じ条件(職種・技術・勤務地・開始時期)でヒアリングし、基準票に募集背景/体制/評価指標/残業の波/ツールとバージョンを同じ形式で記録してください。
派遣は条件と体制の透明度が高いぶん誤差が出にくく、SESは幅が取りやすいぶん事前情報が荒れやすいです。両軸を同じ物差しで比べれば、案件ガチャの温床である情報非対称を最初から崩せます。
すぐに決めないと流れてしまう案件への向き合い方は?
急がせに引っ張られて曖昧なまま入ると案件ガチャになりがちです。
締切が近い案件ほど、最低限の一次情報だけは数字で握ります。募集背景(欠員/増員)、体制(人数・役割・指揮命令)、評価指標(何で合否・評価を決めるか)、繁忙の波(平均とピークの残業)、ツールとバージョン。ここが埋まらないなら見送って構いません。
短期的に逃した痛みはありますが、中期的には案件ガチャを回避した分だけ、職務要約に載せられる売れる実績が増えます。
「単価」と「成長」、どちらを優先するとガチャを避けやすい?
長い目で見ると、再現性のある「成長」を先に置いた方が案件ガチャを避けやすいです。
理由はシンプルで、実績が数字+ツール+役割で語れるほど、次の商談で一次情報をこちらから提示できるようになるからです。もちろん「単価」は大切ですが、最初の1〜2件は「KPI改善」「自動化」「運用SLA」のどれかを数字で積める現場を優先してください。
結果として単価交渉の説得力が増し、案件ガチャに振り回されないキャリア形成に近づきます。
案件ガチャを避けたい人のための完全ガイド、SESと派遣の違い・回避方法・派遣で働く魅力のまとめ
最後に、明日から動ける形で案件ガチャの回避フローを一枚にまとめます。
やることは難しくありません。数字で聞く→顔合わせを設計する→同じ物差しで比べて決める→合意は紙にする、この一本道で十分です。
まずは今日、派遣とSESをそれぞれ1〜2社ずつオンライン登録し、同じ条件で初回面談を入れましょう。面談では募集背景/体制/評価指標/繁忙の波/ツールとバージョンを数で引き出し、基準票に書き込みます。
1週間で2〜4件に絞り、顔合わせの前日までに職務要約(業務→役割→数字→ツールの1段落)と逆質問(最初の30日で期待される成果・任される範囲・残業上限・在宅可否)を用意します。オンラインなら5分の接続リハーサルも忘れないでください。
合意できた内容は、必ず文面に落とします。残業の平均と上限、繁忙期の目安、評価の物差し、ツールのバージョン、在宅の頻度など…ここまで紙に戻れる状態にしておけば、万一ズレても会社経由で静かに修正できます。
就業後は、週次で成果ログを一段落ずつ積み上げましょう。担当機能、前後の数字、使ったツール、関与の深さ。たったこれだけで、次の商談はあなた主導になり、案件ガチャの余白はどんどん小さくなります。
結局のところ、案件ガチャは運ではなく設計です。数字で聞き、段取りで備え、紙で握り、ログで積む。この4つを回していれば、当たり・ハズレに振り回される働き方からは卒業できます。
あなたの次の現場は、もうガチャではありません。設計どおりに、取りにいきましょう!
「IT業界で挑戦したい!」そんな方はキャルにご相談ください
キャルはWeb/オープン系・汎用系・制御組込系・インフラ系と、ITエンジニアの派遣に特化した派遣会社です。
- IT未経験だけど挑戦したい
- スキルアップしながら働きたい
- いろいろな案件から理想の案件を選びたい
- 派遣でも安心して働きたい
など、上記に該当する求職者や転職活動中の方はキャルにご相談ください。
キャルは案件や取引先企業数が豊富なだけではございません。
国家資格を持つキャリアコンサルタントが、就業開始後の不安や困りごとなどの相談に乗りフォローをおこなうなど、安心して就業していただくためのサポートも実施しています。
ITエンジニアは常時募集・入社しているため、未経験でも同期と共に成長できます。
ITの人材不足が社会問題となっている昨今、キャルでエンジニアとして活躍しませんか?
一緒に働けることを楽しみにしています。
\エントリーはこちら/
キャルでITエンジニアに挑戦する