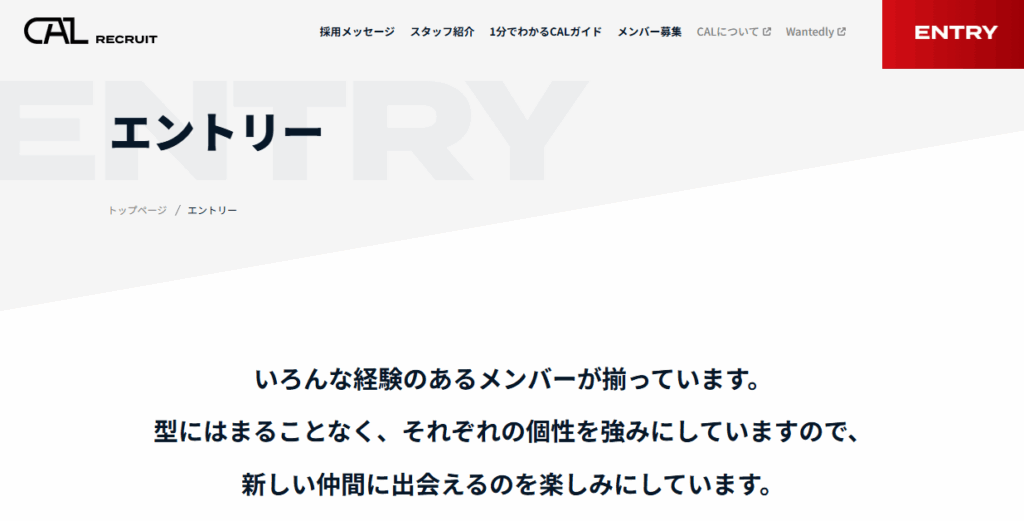みなさんこんにちは。キャル株式会社のゆーな(@cal_public)です。
「カジュアル面談」という言葉をご存知でしょうか?従来の「面接」とは異なり、リラックスした雰囲気の中で企業と求職者がフラットに対話するこの面談形式が、近年急速に広まっています。
本記事では、カジュアル面談の定義・目的から、メリット・準備方法・よくある質問例までを網羅的に解説します。これから就職・転職活動を進める方、または採用担当の方にも役立つ内容となっています。
近年、採用の現場で 「カジュアル面談」 という言葉を耳にする機会が急増しました。選考色を薄めたフラットな対話で、企業は将来の人材プールを拡げ、求職者はミスマッチを防げるという観点から注目されています。
本記事ではカジュアル面談の基礎知識から活用法までを完全ガイドします。
カジュアル面談とは?
採用活動の“入口”が変わる。カジュアル面談とはどんな場なのか?
形式ばらない対話形式の「カジュアル面談」について、その定義と目的を解説します。今注目されている理由も含めて押さえておきましょう。
カジュアル面談とは、企業と求職者が選考に入る前段階でおこなう非選考型の情報交換の場です。従来の「面接」とは異なり、合否を判断するのではなく、お互いの理解を深めることが主目的となります。
企業にとっては、候補者に対して自社の魅力や働き方を丁寧に伝えられる貴重な機会であり、求職者にとっては、求人票やWebサイトだけでは得られない「リアルな会社の雰囲気」を把握することができます。
近年では、採用活動において“ファーストコンタクト”としてこのカジュアル面談を導入する企業が増えており、選考の前段階で信頼関係を築く手段として注目されています。
カジュアル面談の定義と目的
カジュアル面談とは、企業と求職者がフラットな関係で対話をおこない、相互理解を深めることを目的とした非公式な面談です。
一般的に「選考前に気軽に話す場」として設定され、合否の判断をおこなわないことが基本方針です。
具体的には、以下のようなケースで実施されます。
- 企業からのスカウトメールに対するリアクションとして
- 社員紹介制度(リファラル)を通じた候補者との接点として
- 転職フェア・オンラインイベントでの接触後に継続的な関係を築くため
このようなカジュアル面談を通して、企業は「自社に興味を持ってもらえる可能性のある層」に対してアプローチでき、候補者も選考への心理的ハードルを下げて情報収集ができるという利点があります。
企業側では、カジュアル面談の中で「スキルマッチはしていないがカルチャー的にフィットしそう」といった潜在的な人材を見つけ出すことも可能です。
一方、求職者にとっては「話してみたら想像と違った」「想像以上に良かった」といった気づきを得られる貴重な場となり得ます。
カジュアル面談が増加している背景
カジュアル面談が注目され、広く活用されるようになった背景には、採用市場の構造的変化と価値観の多様化があります。
1. 売り手市場における候補者主導の転職活動
特にIT業界や技術職では、人材不足が深刻化しています。そのため、企業が候補者に“選んでもらう”ための努力が不可欠となりました。
「いきなり選考」では、転職意欲が高くない求職者にとって心理的負担が大きく、応募につながらないことも珍しくありません。
カジュアル面談は、そういった層にもライトに接点を持つ手段として効果的です。
2. ミスマッチ・早期離職のリスク低減
内定後に「思っていた職場と違った」と感じて早期離職してしまうケースも少なくありません。
これを防ぐには、事前に企業文化や人間関係、働き方への理解を深めてもらう必要があります。
カジュアル面談は、実際の雰囲気を伝えられる場として有効で、ミスマッチ防止の重要な一手となります。
3. 採用ブランディングや候補者体験(CX)への注目
近年では、採用活動もブランディングの一環と考えられており、候補者に対して「丁寧で親しみやすい印象を与えるか」が企業価値に直結します。
カジュアル面談を通して企業の柔軟性や魅力が伝われば、選考意欲が高まり、志望度が向上することも期待できます。
4. 転職潜在層へのリーチ
「今すぐ転職したいわけではないが、将来的には考えている」という層にとって、いきなりの応募はハードルが高いものです。
カジュアル面談は、そうした層に対し、「まずは話を聞いてみる場」として非常に有効です。長期的な関係構築やタレントプール形成にもつながります。
このように、カジュアル面談は今後の採用活動において重要性を増す“攻めの採用手法”です。
求職者にとっても、企業にとっても、価値のある場として、今後さらに普及していくことが見込まれます。
カジュアル面談と面接の違い
選考ではなく、理解し合う時間。面接とは何が違う?
カジュアル面談は合否を目的とせず、服装や雰囲気も自由度が高いのが特徴です。面接との違いを比較しながら紹介します。
「カジュアル面談って、普通の面接と何が違うの?」と疑問に感じる方も多いでしょう。
実際に両者には共通点もありますが、目的や進行スタイル、心理的な距離感には明確な違いがあります。
このセクションでは、「選考の合否に影響しない」「服装や準備の自由度」といった観点から、面接との違いをわかりやすく解説します。
カジュアル面談を正しく理解することで、より有効に活用できるようになるでしょう。
選考の合否に影響しない
カジュアル面談の最大の特徴は、合否を判断する選考プロセスではないという点です。
つまり、「この面談を通じて不合格になる」「評価される」といったことは、基本的にありません。
※ただし一部企業では、面談後にそのまま選考へ進む場合もあるため、説明や案内をよく確認しましょう。
面接との比較
| 項目 | カジュアル面談 | 面接 |
| 目的 | 相互理解・情報交換 | 合否を決定する選考 |
| 緊張感 | フラット・柔らかめ | フォーマル・高圧的になりやすい |
| 評価 | なし(原則) | あり(評価・選考基準に沿って判断) |
面接では「どう見られているか」「何を聞かれるか」に意識が向きがちですが、カジュアル面談はあくまで双方向の対話。
候補者も企業も、お互いを理解することがゴールです。
そのため、求職者は自分を良く見せようとする必要はありません。
むしろ、「自分にとって合う会社なのか?」という観点から率直に質問をし、自分の価値観を確認する場として活用しましょう。
服装や準備の自由度
もうひとつの大きな違いは、形式のカジュアルさです。
面接ではスーツ着用や履歴書の提出が前提ですが、カジュアル面談では服装や準備内容の自由度が高いことが多く、心理的な負担を感じにくいのが特徴です。
カジュアル面談での服装の例
- 清潔感のあるビジネスカジュアル(ジャケット+シャツなど)
- オンライン面談であれば私服でもOKというケースもあり
- 企業側から「私服でOK」と案内がある場合も多数
とはいえ、あくまでビジネスの場であることに変わりはありません。
「カジュアル=ラフでいい」ではなく、「カジュアル=過度に堅苦しくない」という意味であり、最低限のマナーは意識しましょう。
準備の自由度とポイント
- 履歴書や職務経歴書は不要なケースが多い
- 雑談形式が多いため「聞きたいこと」を中心に準備
- 自己紹介や転職意欲の背景を簡潔にまとめておくと◎
企業から事前に「当日はカジュアルな情報交換の場です」といった案内がある場合でも、「なぜ興味を持ったのか」「どのような働き方をしたいのか」などを簡単に言語化しておくと、面談がより有意義なものになります。
このように、カジュアル面談と面接は、目的・雰囲気・進め方のすべてにおいて異なる側面があります。
「面接ではないからこそ、自分らしく自然体で会話できる」のがカジュアル面談の魅力です。
一方で、「評価されない=何もしなくてよい」というわけではありません。
お互いにとって実りある時間となるよう、適度な準備とマナーを心がけることが大切です。
カジュアル面談のメリット
話すだけで、わかることがある。お互いを知る第一歩。
リラックスした環境で、企業と求職者が本音で話せるカジュアル面談です。その具体的なメリットを紹介します。
カジュアル面談は、単に“リラックスして話せる場”というだけでなく、企業・求職者双方にとって実用的かつ戦略的なメリットを持っているのです。
選考という枠に縛られない自由な対話の場だからこそ、企業側も求職者側も、本音を共有しやすくなり、相互理解を深めることができます。
このセクションでは、カジュアル面談がもたらす主なメリットについて詳しく見ていきましょう。
企業と求職者の相互理解を深める
通常の面接では、「応募者が企業に評価される」という一方向の構図になりがちですが、カジュアル面談は、企業と求職者がフラットな関係性で情報を交換する場です。
これにより、お互いが「相手の価値観やスタンスを知る」ことができ、選考や入社後のミスマッチを未然に防ぐ効果があります。
企業側にとってのメリット:
- 求職者の志向・価値観・キャリア観を把握できる
- フォーマルな面接では見えない人柄や雰囲気を感じ取れる
- 選考前に“カルチャーフィット”の見極めが可能
- 求職者からのフィードバックを得ることで、採用広報の改善にもつながる
求職者にとってのメリット:
- 働く環境やチームの雰囲気を事前に確認できる
- 質問の自由度が高く、自分のペースで不安を解消できる
- 企業の「人となり」が見えることで志望動機が明確になる
例えば、企業説明会や求人広告では見えてこない、「実際のプロジェクトの進め方」「上司との距離感」「働く人たちの雰囲気」などの情報を直接聞けるのは、カジュアル面談ならではの魅力です。
このように、お互いに“選び・選ばれる立場”として対話することで、本質的なマッチングが可能になります。
リラックスした雰囲気での対話
カジュアル面談は、その名の通り“カジュアル=形式ばらない”雰囲気が大きな特徴です。
このリラックスした空気感が、求職者にとっても企業にとっても、大きな利点となります。
緊張せず本音で話しやすい
面接となると、「ちゃんと話さなきゃ」「失敗できない」というプレッシャーがかかりがちですが、カジュアル面談ではそのような緊張感は最小限に抑えられます。
企業側も「雑談ベースで話しましょう」と促してくれることが多く、求職者も自然体で臨むことができます。
リラックスした環境だからこそ、表面的な経歴だけでなく、価値観や悩み、将来像など“深い話”に踏み込むことができるのです。
信頼関係の構築がしやすい
形式的な面接では、どうしても“役割を演じる”ことになりがちですが、カジュアル面談では人間らしさや感情が自然に出やすいため、企業側・求職者側双方にとって信頼関係が築きやすい環境となります。
信頼感がある状態で選考に進むと、質問にも本音で答えやすく、志望動機や将来ビジョンについても具体的に話すことができます。
このように、事前に“良い関係性”が築けていることは、選考後半や内定時の意思決定にもプラスに働くのです。
このように、カジュアル面談は単なる情報交換を超えて、採用活動全体を円滑に進めるための“土台づくり”として機能します。
企業と求職者がリラックスして本音で語り合えることにより、「ミスマッチを防ぐ」「志望度が高まる」「離職リスクが下がる」といった、中長期的なメリットにもつながります。
カジュアル面談の事前準備
「ラフな場」でも、準備の質が印象を変える。
面談の成果は準備で決まる、と言っても過言ではありません。企業研究や質問リストの整理など、当日に備えてやっておきたい準備を解説します。
カジュアル面談は形式ばらない自由な場とはいえ、しっかりと準備して臨むことで、より実りある時間にすることが可能です。
事前に何の情報も調べずに臨んでしまうと、「この会社に興味があるのか不明」「意図が伝わってこない」といった印象を与えてしまい、信頼関係の構築が難しくなります。
このセクションでは、カジュアル面談前におこなっておきたい基本的な準備について解説します。
企業情報のリサーチ
最初におこなうべきなのが、企業に関する情報収集です。
これは面接時の基本ではありますが、カジュアル面談でも同様に重要です。
チェックしておくべき情報
- 企業の基本情報(業種・事業内容・拠点など)
会社概要や代表者メッセージ、企業理念などは公式サイトに掲載されています。 - 最新のニュース・プレスリリース
新規事業の立ち上げや資金調達、組織改編などの話題は、企業の今を知る上で非常に有益です。 - 募集ポジションや職種の内容
求人票が出ていれば、どのような職務内容かを読み込みましょう。現場の課題や求められるスキルを想像しておくと、質問の質も上がります。 - 社員インタビューやSNSの投稿内容
社員ブログやYouTube、X(旧Twitter)などで企業文化を発信しているケースも増えています。現場のリアルな雰囲気が伝わる情報は、志望度を判断する材料になります。
リサーチの目的は「深い会話」のため
カジュアル面談は、単に会社説明を受ける場ではありません。
ある程度の企業理解を深めた上で参加することで、より深く、具体的な質問や対話が可能になります。
事前準備がしっかりしていれば、相手からも「この人は本気で興味を持ってくれている」と好印象を持ってもらえるでしょう。
質問内容の整理
カジュアル面談の最大の価値は、「自由に質問ができること」です。
そのため、事前に聞きたいことを整理しておくことは必須です。面談の時間は限られているため、「あとから調べればよかった」と後悔しないよう、聞きたい項目をメモしておきましょう。
質問を準備する際のポイント
- 選考ではない=本音で聞いていいというスタンスを意識する
- ネガティブなことを聞くのもOK(例:「残業時間」「評価制度の透明性」など)
- 自分の価値観に沿った質問を設定する(例:「自己裁量の幅は?」「チームワークのスタイルは?」)
質問例(目的別)
| 目的 | 質問例 |
| 仕事内容の理解 | 「1日の業務の流れを教えてください」 「配属されるチームの構成は?」 |
| 評価・成長制度 | 「評価面談はどのくらいの頻度でありますか?」 「スキルアップ支援制度はありますか?」 |
| 職場環境 | 「リモートワークやフレックス制度はありますか?」 「オフィスの雰囲気はどのような感じですか?」 |
| 人間関係 | 「どんなタイプの方が多いですか?」 「上司との距離感は近いですか?」 |
質問を投げかけることで、相手の反応や考え方も知ることができます。
自分が本当に働きやすい環境かどうかを判断するために、一歩踏み込んだ質問を心がけることが大切です。
事前準備をしっかりして臨むことで、カジュアル面談は単なる「雑談の場」から、「キャリアを考えるきっかけ」や「理想の職場と出会う手段」へと変わります。
面談の成否は、面談当日だけでなく、事前のリサーチと質問設計の質によって大きく左右されるのです。
カジュアル面談の流れ
話す順番を知っていれば、緊張せずに対話できる。
実際の面談の進行や流れを時系列でご紹介し、オンライン・対面それぞれの進め方のコツも解説します。
カジュアル面談は、自由度が高くリラックスした場であるとはいえ、ある程度の進行フローがあります。
企業によって細かな進め方は異なるものの、基本的には「アイスブレイク → 自己紹介 → 双方の説明・質問 → 締めの挨拶」といった流れです。
このセクションでは、一般的なカジュアル面談の流れをご紹介し、各ステップで意識すべきポイントを解説します。
自己紹介と目的の確認
面談の冒頭は、お互いの簡単な自己紹介から始まります。
堅苦しい経歴紹介ではなく、「どうして今回の面談に至ったのか」という背景や、「どんなことに興味があるのか」といった現在のスタンスを共有することが大切です。
求職者が話すべき内容(例)
- 現在の仕事・業務内容(ごく簡潔に)
- 転職を考えるようになったきっかけ
- なぜその企業に興味を持ったのか
- 今日の面談で聞きたいことや期待していること
例えば、「〇〇業界で営業をしており、業界理解はありますが、もっと企画や事業開発に近い立場で働きたいと感じています。御社の新規事業に興味があり、詳しくお話を伺いたいと思いました」など、自分の関心や目的を率直に伝えると好印象です。
企業側の進め方
企業側からは、以下のような説明がされることが多いです。
- 面談の趣旨(あくまで情報交換の場であること)
- 面談後に選考へ進むかどうかは自由であること
- 今日のタイムスケジュール(例:30分で雑談→10分で質疑応答)
このように、最初に「お互いフラットにお話ししましょう」と伝えてもらえることで、面談全体の空気がやわらぎます。
質疑応答の進行
自己紹介が終わると、次にお互いの興味関心に応じた質疑応答パートに入ります。
ここがカジュアル面談の核となる時間であり、準備してきた質問を活用する場です。
よくある質問内容(求職者側)
- 「御社の〇〇プロジェクトは、どのような体制で動いているのですか?」
- 「若手社員のキャリアステップには、どのような選択肢がありますか?」
- 「現場の方が感じているやりがいや、課題は何ですか?」
回答の内容はもちろん、相手の答え方・雰囲気・表情などから“会社のリアル”が感じ取れるのがこのフェーズの魅力です。
会話のコツ
- 一問一答で終わらせず、「なるほど、ちなみに…」と会話を広げる
- 相手の話に対してリアクションや共感を返す
- 自分の経験と絡めて意見交換をしてみる(双方向性が大切)
また、企業側からも求職者に質問されることがあります。
例えば、「今後どのような働き方をしていきたいとお考えですか?」など、軽いキャリア観を問う質問です。
このときも「完璧な回答」よりも、自分らしい考えを素直に伝えることが大切です。
カジュアル面談は、“聞く”だけでなく“話す”ことで深まる場です。
双方が対話に参加することで、時間の密度も価値も高まります。
面談を終える頃には、「また話したい」「この会社で働く自分をイメージできた」と思えることが理想です。
カジュアル面談での注意点
選考じゃないからこそ、油断が命取りになる。
カジュアル面談でも守るべきマナーや意識すべき姿勢があります。企業視点での注意点と共にご紹介します。
カジュアル面談は「自由でフラットな場」とはいえ、ビジネスの一環であり、マナーやスタンスを誤ると逆効果になるリスクもあります。
特に最近では、企業側が“採用候補としての見極め”を目的にカジュアル面談を活用するケースも増えており、「評価されないから気楽に…」という考えだけでは失敗することも。
ここでは、求職者・企業双方が意識すべき注意点を解説します。
選考の場ではないことを意識する
カジュアル面談は原則として“選考ではない”とされていますが、完全に評価されないとは限らないことを理解しておく必要があります。
特に企業側が候補者を将来的な採用対象と見ている場合、カジュアル面談の中で得た印象が、次のステップに大きく影響することもあります。
求職者側の注意点
- 雑談的な場だからといって、ラフすぎる対応はNG
- 態度が悪かったり、関心が薄そうに見えた場合、「カルチャーが合わない」と判断される可能性がある
- 「選考ではないから何を聞いてもOK」というわけではなく、企業側の配慮にも敬意を払うことが大切
例えば、「福利厚生はいいですか?」「給与は上がりますか?」など、ストレートな質問をぶつけるのは避け、文脈を添えて聞く工夫が必要です(例:「御社で長期的に働く上で重要視されている制度について教えてください」など)。
企業側の注意点
- 「評価しません」と言いながら、無意識に選別の目線で会話をしてしまうことがある
- 説明内容と実態にギャップがあると、後の選考や入社後に不信感を招く
- 候補者の話に一方的なリアクションを返すのではなく、双方向性を意識した進行が望ましい
カジュアル面談は信頼関係のきっかけになる場です。一方通行の“確認作業”にならないように注意しましょう。
企業の現状を正確に伝える
企業側がカジュアル面談でよく犯しがちなミスのひとつが、現場のリアルを美化して伝えてしまうことです。
「候補者の志望度を上げたい」「好印象を持ってもらいたい」という気持ちから、ポジティブな面だけを強調してしまうのです。
しかし、これは大きなリスクでもあります。
なぜ“美化”が問題なのか?
- 実際に入社したあとに「思っていたのと違う」となり、早期離職につながる
- 結果的に会社への不信感を持たれ、口コミサイトなどにネガティブな意見が投稿される可能性がある
- ミスマッチによって、本来マッチしていたかもしれない人材とのご縁を失うことになる
カジュアル面談は、単なるPRの場ではなく、企業文化や働く現場の実情をオープンに伝える場です。
例えば、「現在は仕組みが未整備なところもあり、業務の効率化に取り組んでいる最中です」といったように、課題があることを率直に伝えることは、むしろ信頼につながります。
また、ネガティブな要素にこそ、求職者側が「自分の力で変えたい」と感じるモチベーションの種があることも少なくありません。
カジュアル面談は、お互いが“本音で向き合うための場”です。
だからこそ、過度に気を抜くことなく、相手の立場や心理にも配慮した態度・発言を心がけましょう。
そして、企業側は「現実を見せる勇気」、求職者側は「未来に向けた対話の意識」が大切です。
カジュアル面談での服装
自由と言われても、迷うのが服装。
「私服OK」と言われても何を着ればいいか迷う方に向けて、ビジネスカジュアルのポイントとNG例を具体的に紹介します。
「カジュアル面談って名前だし、私服でいいの?」という疑問を持つ方は少なくありません。
実際、カジュアル面談では服装の自由度が高いケースが多く、企業側から「服装自由」「私服でお越しください」と案内されることも珍しくありません。
とはいえ、“カジュアル”といっても、社会人としての基本的なマナーは必要不可欠です。
このセクションでは、好印象を与える服装選びのポイントと、避けるべき服装の例について解説します。
ビジネスカジュアルの選び方
カジュアル面談の服装で最も無難かつ好印象を与えやすいのが、清潔感のある「ビジネスカジュアル」です。
これは、スーツほどフォーマルではないものの、きちんと感を損なわないスタイルで、男女問わず幅広い場面で活用できます。
男性の場合:
- 襟付きのシャツ(無地 or 控えめな柄)+チノパン or スラックス
- テーラードジャケット(必要に応じて)
- 革靴または落ち着いたデザインのローファー
ネクタイは不要なことが多いですが、心配であれば持参しておき、場の雰囲気に応じて調整しても良いでしょう。
女性の場合:
- シンプルなブラウスやカットソー+スカート or パンツスタイル
- ジャケットやカーディガンで季節感・清潔感をプラス
- ヒールの高さは低〜中程度で、履き慣れた靴を選ぶ
アクセサリーやメイクも控えめにまとめ、全体的に“ビジネス寄りの品のある印象”を意識すると安心です。
オンライン面談のときは?
- 自宅から参加する場合も、画面に映る上半身はビジネスカジュアルで整える
- 部屋の背景にも配慮し、生活感を減らす工夫を
- カメラの高さ・音声テストなど、事前確認も忘れずに
「カジュアル面談だからラフでいい」と思いがちですが、“初対面での印象”は服装から大きく影響を受けるという点を忘れてはいけません。
避けるべき服装の例
極端なラフさは、「社会人としての常識がない」「この人に任せて大丈夫か?」という不安を与える可能性があります。
NGになりやすい服装(例)
| 服装 | 理由 |
| ダメージジーンズ | ラフすぎてビジネスの場に不適切 |
| 派手なTシャツやプリント服 | 企業文化によっては非常識と受け取られることも |
| ノースリーブ、ショートパンツ、ミニスカート | 肌の露出が多い服装は場にそぐわない |
| サンダル・スニーカー | フォーマル感が足りず、軽率な印象を与える場合がある |
| 派手すぎる髪色・ネイル | 業界や企業の雰囲気によるが、控えめにしておくのが無難 |
ファッション系・ベンチャー企業など、服装が自由な社風の場合はある程度カジュアルでも問題ありませんが、「相手企業の文化を尊重した服装選び」が基本です。
「身だしなみ」は自分自身を表す名刺のようなものです。
カジュアル面談では過剰に着飾る必要はありませんが、相手に安心感と信頼感を与える“品のあるカジュアルさ”を心がけましょう。
清潔感・落ち着き・TPOを意識することで、服装から好印象を築くことができます。
カジュアル面談後のフォローアップ
面談後が、本当の勝負かもしれない。
カジュアル面談後の行動で印象が大きく変わります。お礼メールや次のアクションの伝え方をチェックしましょう。
カジュアル面談は形式ばらない場であるため、「終わったらそれで終了」と考えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、面談後のフォローアップは今後の選考や関係構築にもつながる重要なステップです。
このセクションでは、カジュアル面談後に実施すべき行動として、お礼メールの送り方や次のステップへの意思表示の仕方を詳しくご紹介します。
お礼メールの重要性
カジュアル面談後にお礼メールを送ることは、ビジネスマナーとして非常に大切です。
形式的なものであっても、丁寧なメールは好印象を与えますし、「話を聞いて満足して終わり」ではなく、「今後につながる姿勢」を示すきっかけにもなります。
お礼メールのポイント
- 面談当日〜翌日までに送るのがベスト
時間が経ちすぎると誠意が伝わりづらくなります。 - 件名はわかりやすく簡潔に
例:「【カジュアル面談のお礼】〇〇(氏名)です」 - 本文は3ステップで構成するとスマート
① 面談のお礼 → ② 印象的だった内容 → ③ 今後の希望や感想
メール例(求職者から企業へ):
件名:カジュアル面談のお礼(〇〇)
株式会社〇〇
〇〇様
本日、カジュアル面談のお時間をいただきありがとうございました。
貴社の事業内容や今後の展望について直接お伺いでき、大変参考になりました。
特に、社員の自主性を尊重した働き方や、少数精鋭で動いている新規事業の内容に強く興味を持ちました。
ますます貴社で働いてみたいという気持ちが強まりました。
今後ご縁がありましたら、ぜひ選考に進ませていただけますと幸いです。
引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
〇〇(氏名)
メールアドレス/電話番号
このようなメールを送るだけでも、相手への印象がグッと良くなります。
次のステップへの意思表示
カジュアル面談のあと、「選考に進むかどうかは自由」というケースも多く、自分から次のアクションを示すことが必要になります。
よくある3つの選択肢と対応方法
| 選択肢 | 行動例 |
| 1. 選考に進みたい | → 面談後すぐに意思表示をする(お礼メールに記載するのがスマート) |
| 2. 一旦保留したい | → 「引き続き検討させていただけますと幸いです」と丁寧に伝える |
| 3. 辞退したい | → 感謝の気持ちを伝えた上で、辞退の意思を明確に伝える(マナーを守る) |
「選考に進まない=失礼」ということではありません。
カジュアル面談はあくまで相互理解の場なので、合わないと感じた場合も、率直に、かつ礼儀正しく意思を示すことが社会人としての基本です。
面談の終了後こそ、“印象の定着”が起きる重要なタイミングです。
最後まで誠実かつ丁寧な対応を心がけることで、採用担当者や現場担当者との信頼関係が深まり、次のステップへの流れもスムーズになります。
カジュアル面談の活用方法
“応募”の前に、“接点”をつくる。
転職活動・採用活動の戦略的な一手として、カジュアル面談をどう活用すべきか、求職者・企業両視点から解説します。
カジュアル面談は、単なる事前説明の場にとどまらず、転職活動や採用活動において大きな戦略的価値を持つツールです。
情報交換という位置づけだからこそ、求職者と企業の双方にとって“リスクのない出会い”を生み出せるのが最大の魅力です。
このセクションでは、求職者・企業それぞれの立場から、カジュアル面談をどのように有効活用できるのかを解説します。
転職活動における活用法
近年では、転職活動の早い段階でカジュアル面談を活用する求職者が増えています。
求人に応募する前に企業と接点を持つことで、“応募先を見極める力”を養うことができるからです。
カジュアル面談を活かす3つのポイント
- 「応募前の情報収集」として活用する
選考前にリアルな社風や職場環境を知れる貴重な機会です。
求人票や企業サイトだけではわからない情報に触れることで、ミスマッチを防げます。 - “本命企業”の志望度を高めるために使う
面談を通じて企業理解を深めることで、応募時に質の高い志望動機を記述できます。
実際に話した担当者とのエピソードを絡めると、志望度の説得力も格段に上がります。 - キャリアの可能性を広げる機会とする
「すぐに転職を考えていないけど…」という段階でも、情報交換をすることで将来の選択肢を広げられます。
場合によっては、企業側から逆にオファーがくることもあります。
求職者にとってのメリット
- プレッシャーが少ない環境で自分の考えを整理できる
- 気になる業界の内情を、一次情報として得られる
- 親身な企業と出会えるきっかけになる(応募者を大切にする会社かが見える)
このように、「応募する・しないにかかわらず価値がある」のがカジュアル面談の本質です。
企業側の採用戦略としての活用
企業にとっても、カジュアル面談は「採用広報」と「母集団形成」の両方を担う有力な手段です。
従来の“応募があってから動く”採用手法に対し、先回りして候補者と接点を持つ=攻めの採用を実現できます。
採用活動への具体的な効果
| 活用方法 | 効果 |
| 気になる候補者へアプローチ | スカウトメール後の第一接点として活用できる |
| 転職潜在層の掘り起こし | 今すぐ応募しない層ともつながりを築ける |
| 応募率の向上 | カジュアル面談後に応募につながるケースが多い |
| 採用ブランディング | 社員のリアルな声を伝えることで好印象を残せる |
カジュアル面談を導入する企業が増える背景
- 採用競争の激化により、母集団形成の多様化が求められている
- 転職市場の流動性が高まり、「転職検討中層」へのリーチが重要になってきた
- オウンドメディア採用やSNS採用と相性が良い
また、カジュアル面談は、現場社員や若手社員が登場することで、応募者の“心のハードル”を下げやすいという特徴もあります。
求職者にとっては“転職活動の羅針盤”、企業にとっては“採用戦略の突破口”となるのがカジュアル面談です。
お互いの温度感や価値観を近づけるこの仕組みは、現代の採用における「接点づくり」の主流となりつつあります。
カジュアル面談に関するよくある質問
カジュアル面談は近年一般化しつつあるものの、まだまだ疑問や不安を抱える求職者は多くいます。
特に「選考に関係あるの?」「落ちることはあるの?」「どんな準備が必要?」といった質問は非常に多く寄せられています。
このセクションでは、実際に多くの方が感じている代表的な質問をピックアップし、明確にお答えします。
カジュアル面談で落ちることはあるの?
基本的にカジュアル面談は「選考を目的としない情報交換の場」とされています。
そのため、「合否をつける」という意味で“落ちる”ことはありません。
しかし、以下のようなケースでは、事実上の「不採用判断」がなされることがあります。
企業側が選考を見据えて面談を実施している場合
企業によっては「応募前にカジュアル面談を挟むことが必須」というフローを取り入れているケースもあります。
この場合、面談を通じて以下のような判断をしている可能性があります。
- 自社のカルチャーと合いそうか
- 転職意欲がどの程度あるか
- 基本的なコミュニケーション能力があるか
その結果、面談後に選考案内がなかった場合は、「この方は現時点では見送りたい」と判断された可能性も考えられます。
「落ちる」ことよりも大切なこと
カジュアル面談の本来の目的は、ミスマッチの防止と相互理解の促進です。
そのため、お互いの価値観や将来の方向性が合わないと感じた場合は、無理に次のステップに進む必要はありません。
つまり、「落ちた」「選ばれなかった」というよりも、「今回はお互いに合わなかった」と捉えるのが適切です。
カジュアル面談の流れは?
カジュアル面談は企業によって進行の仕方が多少異なりますが、一般的には以下のような流れで進むケースが多いです。
一般的なカジュアル面談の流れ(30〜60分)
| 時間配分 | 内容 |
| 最初の5〜10分 | アイスブレイク、自己紹介、面談の目的説明 |
| 中盤の20〜40分 | 双方からの質問・回答タイム(双方向) |
| 最後の5〜10分 | 面談のまとめ、次のステップについて確認・挨拶 |
オンライン面談のケース
近年ではZoomやGoogle Meetを使ったオンラインでの実施が一般的になっています。
画面越しの対話では表情や声のトーンがより重要になるため、カメラ・マイクの設定や背景環境にも気を配りましょう。
注意点
- 一問一答にならず、会話を広げる意識を持つ
- 時間配分に余裕を持ち、聞きたいことをあらかじめ整理しておく
- 「話しすぎ」にも注意し、相手の話を引き出す配慮も大切
事前に流れをイメージしておくことで、当日も落ち着いて対話に臨むことができ、本来の自分らしさを発揮しやすくなります。
カジュアル面談とは?のまとめ
カジュアル面談は、これまでの“選考ありき”の採用プロセスとは一線を画した、新しい出会いの形です。
企業・求職者の双方にとって、リスクを抑えながらお互いの理解を深められる貴重な機会であり、今後の転職・採用市場でますます重要性が高まることが予想されます。
本記事では、カジュアル面談の定義から面接との違い、メリット、活用法、実際の流れ、注意点に至るまでを総合的に解説しました。
最後に、カジュアル面談の重要性と、今後に向けた準備のポイントを簡潔に振り返ります。
カジュアル面談の重要性
- 求職者にとっては、「応募前に企業を見極める」チャンス
- 企業にとっては、「母集団形成」「採用ブランディング」の戦略的施策
- 相互理解をベースにしているため、入社後のミスマッチ防止につながる
従来の履歴書・職務経歴書だけでは伝わらない「人となり」や「社風」といった、定量化しにくい要素を補う手段として、今後さらに浸透していくでしょう。
特にIT・スタートアップ・ベンチャー業界では、カジュアル面談を導入する企業が続々と増加しており、応募前接点の標準化が進んでいます。
次のステップへの準備
面談後に何もしなければ、それで終わってしまいます。
求職者ができること:
- 面談内容を振り返り、自分のキャリア観と照らし合わせる
- お礼メールを送り、選考への意思表示を明確にする
- 必要に応じて複数社と面談を実施し、自分に合う会社を見極める
企業がすべきこと:
- 面談後の対応(選考案内 or 丁寧な見送り)を迅速におこなう
- フィードバックを活用して、今後の採用活動の改善に活かす
- 面談参加者の意見を記録し、候補者管理のデータベースとして蓄積する
カジュアル面談は、採用活動・転職活動の「入口」にすぎません。
しかし、この入口での印象や準備の精度が、その後のステップの成否を大きく左右します。
双方が誠意をもって向き合い、「出会いの質」を高める努力を続けることで、ミスマッチのない理想的な採用が実現するでしょう。
キャルでもカジュアル面談を実施しています!
キャルでもカジュアル面談を実施しています!
弊社はITエンジニアの派遣に特化した人材派遣会社で、エンジニア以外にも営業職や採用職などの職種も随時募集中です。
- 応募する前に質問したいことがある
- マッチするかを確認した上で応募するかを決めたい
- 教育や育成体制についてあらかじめ知りたい
- ホームページに載っていた〇〇について聞きたい
このようにお考えの求職者や転職活動中の方は、一度カジュアル面談をしてみませんか?
面談では仕事内容やキャリアの可能性、働き方などを率直にお伝えし、ご不安やご質問にも丁寧にお答えいたします。履歴書やスーツのご準備は不要です!
少しでもご興味をお持ちいただけましたら、以下のエントリーページに入っていただき、ご質問欄に「カジュアル面談希望」と記載の上お申し込みください。
お話しできることを心より楽しみにしています!
\ぜひ一度お話ししましょう!/
カジュアル面談を申し込む